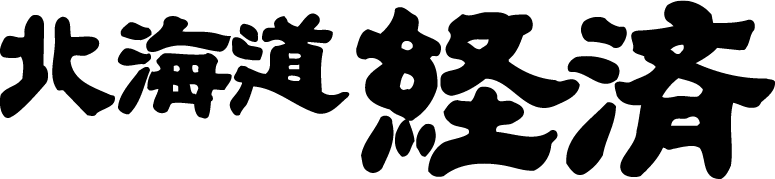1945年8月。第二次世界大戦の終結から程なくして、旧大日本飛行協会(東京・芝田村町)跡の瓦礫の山にたたずむ一人の男がいた。旭川市(東旭川村)出身で〝空に生き、空に殉じた男〟中野勝義(写真)。後に全日空の前身となる日本ヘリコプター輸送㈱を、美土路昌一(全日空初代社長)とともに設立した民間航空の先駆者だ。「ケタ外れの社員」と美土路に呼ばしめた、その破天荒な偉人が刻んだ足跡は多彩なエピソードに彩られている。(敬称略)
東高でのあだ名は「村長」
東旭川村で1904(明治37)年に屯田兵の三男として生まれた中野は、旧旭川尋常高等小学校時代から優秀な成績で、愛情と正義感が強く特異な存在だった。良くも悪くもボス的な存在で、周囲が彼を自然に持ち上げた。その行動は教師らの注目の的となり、しばしば話題にのぼった。
 学校の児童劇では楠木正成・正行父子の「湊川の別れ」やカチカチ山の童話など、教科書に出てくる内容が主にストーリーとなっていたが、中野はどの劇でも主役に選ばれた。中野と少年時代をともにした加藤精一は、寄稿誌「中野勝義の追憶」(中野勝義追憶録刊行会編)の中で「彼の企画センス、独創的な演出力は、すでにこの頃から芽生えていた。どうしたら見せ場をアピールできるか、セリフや演技には少年らしい頭を使って、場内を沸かせた」と語っている。
学校の児童劇では楠木正成・正行父子の「湊川の別れ」やカチカチ山の童話など、教科書に出てくる内容が主にストーリーとなっていたが、中野はどの劇でも主役に選ばれた。中野と少年時代をともにした加藤精一は、寄稿誌「中野勝義の追憶」(中野勝義追憶録刊行会編)の中で「彼の企画センス、独創的な演出力は、すでにこの頃から芽生えていた。どうしたら見せ場をアピールできるか、セリフや演技には少年らしい頭を使って、場内を沸かせた」と語っている。
東旭川地区は、中野が少年のころ、水質が悪く鉄分を含み飲料水としてあまり適さなかったため150㍍離れた井戸への水汲みと水運びの仕事が、中野少年の日課になった。成人してからは山葡萄やコクワの実で酒を作る名人となったが、山葡萄やコクワの実に親しんだのも少年時代からだった。
15歳を過ぎた中野は、「見事な発育ぶりで、腕自慢の彼は、よく級友に力こぶをふくらませて、『米の一俵や二俵かつげなくて男といえるか』と小鼻をふくらませ楽々と俵を持ち上げた」(加藤)。
旧制旭川中学校(現・旭川東高校)に入学し、付いたあだ名が「村長」。
義に厚く親分肌で、ズボンのポケットに両手を突っ込んで胸をそらし悠々と歩く姿は、村長然としていたようだ。相手を威圧するのではなく、いつも微笑みをたたえていたという。
後に「空の軍神」と呼ばれる加藤建夫とは同期生だった。シベリヤ事変でいち早く偵察飛行に出征したことでも知られた海軍少佐の赤石久吉が、同校を訪れ、飛行機の話をした際には、とりわけ中野と加藤が熱心に聞き入ったと伝えられる。
「神風号」でロンドンへ
旭川中学校を卒業すると一時、旭川米飯第一小学校の代用教員となったが、当時ネガティブな内容の歌詞で人気を集めていた流行歌「船頭小唄(枯れすすき)」を教えて辞職を余儀なくされたことは、さすがの中野も苦い経験になったようだ。
だが、その後、法政大学に進むと、他の大学にはない「航空研究会」を発足させ、時代の最先端を歩むことになる。学生ストライキを組織し暴れん坊ぶりを発揮したり、日本で初めての大学通信教育にも力を尽くした。
卒業後、朝日新聞社に入ると、社内に「航空部」を創設、民間航空の発展に情熱を燃やす。美土路(全日空初代社長)は、中野について前出の寄稿誌の中で、こう回想する。「入社当時からガラガラ声で、野人そのままの風貌の上に毎日、大酒は飲む、乱酔はする。酔えば必ず先輩に議論を吹っかけ、さらには頭から罵倒するという誠にケタ外れの社員であった」。

この続きは月刊北海道経済2018年10月号でお読み下さい。