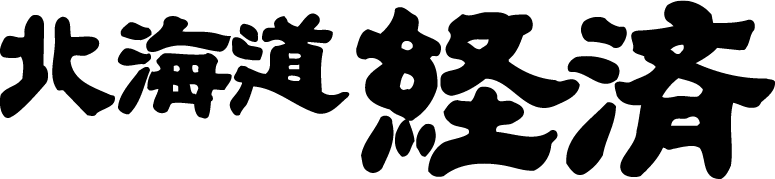旭川市は、今年度から「果樹産地強化支援事業」をスタートさせた。黄色い品種をはじめ8種のリンゴなどを〝有望品種〟と位置づけ、その導入を市が支援するというものだ。助成の対象を果樹に絞ったのは今回が初めて。「果樹には人を呼び込める魅力があり、まちのイメージアップにもつながる」と生産者の取り組みをバックアップする試みで、「『果樹のある街・旭川』として市民に愛される産地づくり」を目指す。
有望品種をピックアップ
旭川における果樹栽培は1892年、上川御料地内に設けられた果樹園で各種果樹が試験的に栽培されたことが始まりとされる。
その後、神居、神楽地区に開拓者がリンゴを植えたものの、凍害のために実を結ばなかった。1907年に入り、神居古潭に植えたリンゴの中に適した品種があったため栽培面積が拡大し、しだいに産地が形成された。ピーク時の昭和20年代には、旭川市内に果樹園が40数軒あった。
現在、旭川における観光果樹の中心品目とされるのがサクランボ。もともとは自家用で、防風林代わりに植えられていたが、昭和40年代に販売用として植栽が進んだ。とりわけ神居産サクランボは知名度があり、関西方面で人気だ。
一方、市内における果樹の栽培面積は減少の一途をたどり、現在、リンゴの24㌶をはじめ、サクランボが23㌶、ナシ5㌶、ブドウ1㌶、プルーン・スモモが1・2㌶、その他(ブルーベリー、ウメなど)で合わせて57・8㌶。
 深川や増毛、余市などの例が示すように、果樹はまちおこしの一翼を担い、まちの魅力を高める農産物として評価されている。しかし、旭川では他の農産物に比べ、産地規模が小さいだけでなく、市民からの認知度も低い。
深川や増毛、余市などの例が示すように、果樹はまちおこしの一翼を担い、まちの魅力を高める農産物として評価されている。しかし、旭川では他の農産物に比べ、産地規模が小さいだけでなく、市民からの認知度も低い。
旭川の果樹生産農家は、それぞれ独自の品種を植栽しており、「旭川はこれ」という特徴的な品種がないのが実情。まとまった収量を確保できず、若木が多く、栽培面積あたりの生産量も少ない。
リンゴの生産農家は現在、神居町や東旭川など市内で7軒。1軒あたり20品種のリンゴを栽培し、多いところでは50種類も栽培している農家がある。それぞれ直売所やリンゴ狩りなどの軒先販売を中心に経営してきたが、JAを通じた市場出荷を一部行っているケースもある。
そんな中で、「リンゴの北限」をキャッチフレーズに、組織ぐるみで果樹生産事業に取り組む増毛町の気概にも触発され、旭川の果実生産者たちが「産地づくりに向けて共同で取り組み、品種を絞り込んで旭川ならではのブランドをつくっていこう」と一念発起した。
産地としての競争力を高めるべく、旭川市果樹協会(事務局・市農業振興課)が主体となり、着手することになったのが、今回の「果樹産地強化支援事業」だ。予算規模は約230万円と決して多くはない。ただ、市がこうした団体の事務局を担当するというのは異例の措置ともいえ、積極的な姿勢がうかがえる。
(この続きは月刊北海道経済8月号でご覧ください)