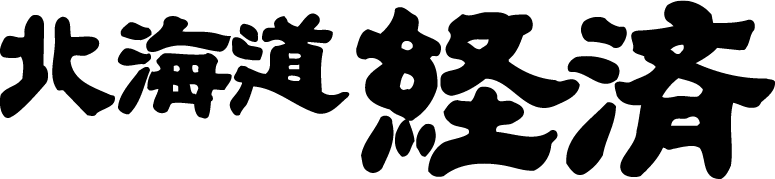清楚なルックスと「恨み節」とも呼ばれるハスキーな歌声で人気を集めた歌手の藤圭子さん(旧姓・阿部純子、享年62)が8月22日、衝撃的な死をとげた。「圭子の夢は夜ひらく」などのヒット曲で1970年代に一世を風靡した彼女は、多感な少女時代を旭川で過ごした。薄幸の女性のイメージで、独特の哀愁をにじませた昭和の歌姫に、この旭川の地はどんな影響を与えたのだろうか。
美談はない
藤圭子さんは8月22日朝、東京・西新宿にある28階建て高層マンションの13階の一室から、黒っぽいTシャツに短パン姿で飛び降り、搬送された病院で亡くなった。現場の西新宿は、デビュー当時、藤さんが活動拠点にしていた思い出の地でもあった。
近年、表舞台から遠ざかっていた藤さんは今年3月、藤さんを世に送り出した育ての親でもある作詞家の石坂まさをさん(享年71)が亡くなった際にも葬儀に姿を見せず、消息が不明。奇しくも、8月23日に都内で「石坂さんを偲ぶ会」が開かれる、その前日に旅立ってしまった。
故人の遺志により、知人、友人の面会は受け付けず、葬儀は営まれなかった。火葬のみを行い、親族だけで荼毘(だび)に付す形となった。
藤さんの訃報をテレビのニュースで知った旭川市神居町の長井孝之さん(70)は次の日、神居神社の境内に一人たたずんだ。「誰が何と言おうと大ファン」という長井さんは、藤さんが小学生のときに、神社で行われた歌謡大会で見事優勝を飾った際の彼女の面影を求めて「あの日」と同じ場所に立った。
「神居祭り」の一環として実施された歌謡大会は、土俵の上に設置されたステージで繰り広げられ、藤さんは継ぎはぎだらけの服装で美空ひばりの「りんご追分」を熱唱。その姿を境内のトドマツに寄りかかりながら、じっと見ていた長井さんは「この子は絶対にプロの歌手になる」と、その場で確信したという。
神居祭りは平成に入ってから、「ふるさとカムイふれあいフェスティバル」と名前を変えているが、毎年9月1日に実施。ここ10年以上、祭りの日に雨が降ったことはなかったというが、今年その日、イベントの終盤に雨が降り始め「圭子の涙雨か?」と話題になった。
同フェスティバルの実行委員長、石坂辰義さんは「藤圭子がここで育ったことは、地域の自慢で尊敬の念もあるが、あの子のことを語り出すと、美談といえるものはなく、同情心ばかり湧いてくる。小さなときから大人の顔をしており、歌はピカイチだったが、祭りの浴衣は模様なんだか、汚れの染みなんだか分からないような粗末な恰好をしていた」。
祭りに参加したある神居町の住民は「周りから持ち上げられ、サムライ部落で育った日銭生活から、いっぺんに花形スターになってしまったため、そのジレンマに陥り自ら命を絶ってしまったのではないか」と今回の訃報をとらえる。
神居中の同窓会長、上楽(じょうらく)隆利さん(71)は、藤さんが中学生のときに神居神社の踊り場で歌った姿が印象的で「顔もきれいだし、歌も上手だったから、しっかり見た」。父親の国二郎さんは、浪曲歌手としてだけでは食べていけず左官の仕事もしており、農閑期には「私も一緒に仕事をしたことがある」と当時を振り返る。
7歳から流し
 藤さんは1951年、岩手県一関市で地方まわりの浪曲歌手だった父・松平国二郎さん(本名・阿部壮)と、目が不自由な三味線奏者の母・竹山澄子さん(同・阿部澄子)との間に、巡業の途中、3人きょうだいの末っ子として生まれた。
藤さんは1951年、岩手県一関市で地方まわりの浪曲歌手だった父・松平国二郎さん(本名・阿部壮)と、目が不自由な三味線奏者の母・竹山澄子さん(同・阿部澄子)との間に、巡業の途中、3人きょうだいの末っ子として生まれた。
一家は、藤さんが生後まもなく渡道。3歳のときに旭川に移り住んだ。生活は苦しく、道内や東北を中心に旅回りをし、祭りや炭鉱、寺の本堂、旧家の大広間などで歌をうたい、その日暮らしをしていた。
仕事がないときは、長女に乳飲み子の藤さんを背負わせ、澄子さんは三味線を抱え、国二郎さんは長男・博さん(のちの歌手・藤三郎)の手を引き風呂敷包みを背負いながら、一軒一軒営業のために農家をまわった。
忠別橋たもとのサムライ部落で生活していた際には、「冬、下駄で忠別川の氷を割って、おしめを洗っていた」と当時の様子を知る人は話す。
やがて藤さんも家族を支えるため、7歳ごろから両親と一緒に演歌の流しを始めた。マイナス20度の厳寒の折でも、膝まで雪に埋もれながら、何時間も歩き、寺の軒先や床下で寝ることもあった。
藤さんは小学校を何ヵ所か転校したが、大有小4年のときの担任だった小田栄一郎さん(81)は、同校に編入してくる際、在学証明書を一度に4、5枚も重ねて提出してきたことにまず驚かされる。
旭町にあった住まいは、畳もなく、床がむき出しになった状態で、裸電球が一つぶら下がっていたにすぎない。それでも家族5人寄り添いながら暮らしていた。
近くに住んでいた小林芳子さん(87)は、長男の三郎さんと藤さんが納豆や豆腐を売り歩いていた姿を記憶。殿村真紀子さん(64)は「自分から明るくあいさつしてくることもあれば、声をかけても何もしゃべらないことがあり、あのころから躁鬱の気があったかもしれない」と振り返る。
貧しさのせいか、ある年のクリスマス、近くの菓子店で姉妹2人そろってケーキをごっそり「拝借」してしまったことは、知る人ぞ知る語り草になっている。
遠足など費用のかかる学校行事はすべて欠席。服装は一年中、穴のあいた同じものを着てくるほど生活が困っていた様子で、靴もゴムの底が「カッパカッパ」と音を立て、取れそうだった。
(続きは月刊北海道経済10月号でお読みください)