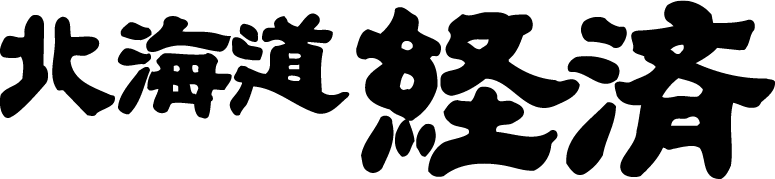全国ニュースに「旭川医大」が連日登場している。パワハラ発言疑惑、医師派遣先病院からの「アドバイス料」約7000万円…。多くは吉田晃敏学長個人にまつわるものだ。さらに、本誌に寄せられた情報をもとに調査を進めたところ、旭川医大病院で吉田学長を患者とする向精神薬の処方箋が大量に発行されていた疑いが浮上した。担当した医師の多くが、吉田学長の「牙城」である眼科に所属している若手であることから判断して、学長本人が医師に圧力をかけて処方させた可能性もある。学長の飲酒問題はもはや医大関係者の多くが認めるところだが、同時に吉田学長は向精神薬の依存症にも陥っていたのではないか。大量の処方箋が誰の手でどのように発行されたのか、旭川医大病院や学長選考会議は本格的な調査を行う必要がある。
頻繁に向精神薬 適正量の4倍以上
本誌の調査結果によれば、吉田晃敏旭川医科大学学長は、少なくとも2019年の秋ごろまで、旭川医科大学病院で患者として診察を受け、向精神薬の処方を受けていた。もうすぐ69歳となる吉田学長は「立派」な高齢者。体にさまざまなトラブルが生じて受診するのは自然なことだが、奇妙なことがある。
本誌が注目したのは「ベンゾジアゼピン系向精神薬」にグループ分けされる2種類の薬。どちらも同様の仕組みで体に作用し、不眠症の治療薬として使われることが多い。以下、問題の2種類の薬をA、Bとするが、Aは超短時間型、Bが短時間型と、効果を発揮する時間に違いがある。
 薬品にはそれぞれ「最大内服量」が定められている。患者としては苦痛から脱するために多く服用したくなることもあるが、一定以上の量を摂取すると副作用が発生し、病気を治すどころか健康を害してしまう。A、Bについても最大内服量が定められており、メーカーが発行する添付文書、つまり薬品の取扱説明書に明記されている。この最大内服量の範囲内で処方するのは、医師にとっては常識中の常識だ。
薬品にはそれぞれ「最大内服量」が定められている。患者としては苦痛から脱するために多く服用したくなることもあるが、一定以上の量を摂取すると副作用が発生し、病気を治すどころか健康を害してしまう。A、Bについても最大内服量が定められており、メーカーが発行する添付文書、つまり薬品の取扱説明書に明記されている。この最大内服量の範囲内で処方するのは、医師にとっては常識中の常識だ。
なぜかこの常識が、吉田学長に対しては守られなかった。2019年の7~10月、Aについては4.5倍。Bについても2倍近くが処方されていた。この状況についてある医師は、「吉田学長は依存症だったのだろう」との見方を示す。
しかし、旭川医大病院では、こうした過剰投与に二重三重のチェックがかかる。まず、規定の量を上回る処方には、薬剤部から注意が入る。これは医療事故を防ぐのが目的。また、向精神薬のような依存症や中毒の恐れがある薬品については、一度に30日分を超える処方ができないしくみになっている。さらに、規定を上回る量の投薬を行っても患者の健康状態が改善するとは期待できないため、レセプト審査ではねられる。担当医からきちんと説明が行われない限り、この投薬については健康保険からの支払いが行われない。
にも関わらず、二つの薬品の処方は続けられた。「30日」の制限は、「30日分」の処方箋を短期間のうちに何度も発行することで回避された。患者の「学長」という立場が影響したのだろうか。
後任眼科教授 突然退任の謎
とくに注目すべきは、投与されたのが「ベンゾジアゼピン系」の向精神薬だということだ。ベンゾジアゼピン系は取り扱いが難しい薬。Aの添付文書の冒頭には「本剤の服用後に、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)があらわれることがある。また、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるので注意すること」と赤字で記載されている。さらに、「本剤に対する反応には個人差があり、また、もうろう状態、睡眠随伴症状(夢遊症状等)は用量依存的にあらわれるので、本剤を投与する場合には少量から投与を開始すること。やむを得ず増量する場合は観察を十分に行いながら慎重に投与すること。ただし、「最大内服量」を超えないこととし、症状の改善に伴って減量に努めること」とある。にもかかわらず、吉田学長には大量のAが処方されていた。添付文書の警告する通り、もうろう状態などの副作用が「用量依存的」にあらわれていた可能性があるし、こうしたリスクを、処方した医師が知らなかったはずはない。

この続きは月刊北海道経済2021年03月号でお読み下さい。