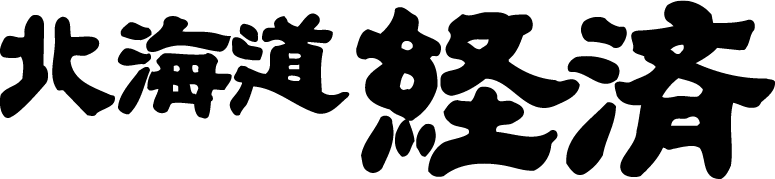旭川の隣町・比布町の伝統園芸として知られるいちご栽培。生産者の高齢化と後継者不足で栽培農家の数が減少する中、産地衰退に歯止めをかけようと立ち上がったのが町の若手生産者たち。寒冷地では珍しい「冬いちご」の実証栽培に試行錯誤しながら取り組み、4年目を迎えた今年は収穫がすこぶる順調。当初目標だった1.2トンの収穫量を超えそうな勢いだ。

最盛期には66軒
比布町でいちごの栽培が始まったのは、1921年(大正10年)頃。子供たちのおやつのために生産者が自家用に栽培していたが、果実が美味しく育てやすいことから商品化が進み、加工品も開発されるようになった。1975年には、収穫したてのいちごを味わえる「いちご狩り」がスタートし、現在では旭川をはじめ札幌などの道央エリアや、北見、網走、釧路などの道東からもドライブがてらにやってくる人が増え、毎年1万人が利用する人気のレジャーとして定着している。
しかし、この人気に反比例するように、いちご農園の数は減少傾向にある。稲作や畑作といちご栽培を兼業している生産者が多いために、田植えの時期といちごの収穫が重なってしまうことが生産者を悩ませてきた。
またいちご栽培は手作業が多い。苗植えをはじめ、余分な葉や花の摘み取り、マルチ(ビニール膜)を苗にかけてからカッターで穴を空けて苗を一つずつ取り出す作業など、すべて手で行う必要がある。そのため、労力のかかるいちご栽培に見切りをつけ、野菜や花卉(かき)に転じる生産者が増え、いちご農家の数は減少してきた。これに生産者の高齢化と後継者不足が拍車をかけ、ピーク時には66軒あったいちご農家は、現在では15軒に満たず、このまま減少が進めば、産地衰退の危機に陥る可能性は否めない。
危機感を抱いた比布町では2018年、産地復活のために農協や農業試験場などと連携してプロジェクトチームを結成。農作業の閑散期となる冬場にいちごの収穫がピークを迎える「冬いちご」の実証実験栽培に着手することにした。
1年目は150キロ
これに手を挙げたのが、町の30代と40代の若手生産者たち。町で穫れた農産物の直売所「ナナプラザ」(比布町新町4)を運営する農業生産法人ネクスピークのメンバー5人が町の委託を受け、道北エリアのように寒冷地では先例の少ない冬いちご栽培に2019年に着手した。
品種は「紅ほっぺ」。大ぶりで縦長の果実が特徴で、鮮やかな紅色をして、いちご特有の甘さと酸っぱさを味わうことができる品種だ。
1年目は、直売所の裏手の土地にビニールハウスを設置し、9月に2200本の苗を定植。1200キロの収穫を目指したものの、収穫量は150キロと目標を大きく下回った。
2年目の20年は、前回よりも1ヵ月早い8月中旬に定植。生育は順調だったものの、秋になると葉が黄色に変色。ハウス内に換気機能がなかったために高温になり過ぎたり、水やりに使用している地下水がいちごの生育には向かないアルカリ性に傾いてしまったことが原因だったようで、収穫量は600キロと目標の半分にとどまった。
1年目と2年目で直面した課題を改善した3年目の21年は収穫量が一気に増大し、規格外品も含めた収穫量は1080キロと初めて1トンの大台に到達した。
好調なスタート
4年目となる今季の栽培はすこぶる順調だ。昨年8月下旬に苗を定植。9月には、栄養分が奪われないようにランナーと呼ばれる茎や古い葉を取り除く作業をくり返し、10月には病害や害虫を抑制するために防除。マルチを貼って保温と保湿をした。開花は11月。12月には芽摘みを行って、実らせる実の数を制限した。一般的にいちごを市場に出荷する時には、果実がまだ白い段階で収穫し、パックに詰めて出荷する。しかし同法人では、直売所で販売している強みと、特産品として人気を確立するためにも本当に美味しい果実を食べてもらおうと考え、真っ赤に熟すまで育て、完熟したものをその日の朝に摘み取って販売している。
今年の初収穫は1月14日。甘酸っぱい質の良い果実が次々と実り、22日には1日に20キロを収穫。今季の目標は、1季目から目指してきた収穫量1200キロを達成すること。2月21日時点で、すでに収穫量は300キロを超えている。冬いちごの収穫は3月から4月がピークで、この調子で行けば目標は達成できそうだ。
三重構造のハウス
4年目にしてついに軌道に乗った取り組みだが、寒冷地では珍しい冬いちごの栽培に、どのようにして成功したのだろうか。2月下旬にビニールハウスでの栽培の様子を見学させてもらった。
案内をしてくれたのは同法人取締役の片澤英幸さん(42)。片澤さんの実家では20年ほど前から、町の特産品の「千本ネギ」を生産しているが、片澤さんは学校卒業後、市外の大手食品メーカーの工場に勤務。8年前に帰郷してから就農したUターン組だ。
ビニールハウスの中では、「高設栽培」という方法でいちごが栽培されており、片澤さんの腰の高さの位置にある台には2200本の苗が植えられ、真っ赤に熟した大振りのいちごや、まだ青い実がたわわに実っている。一粒試食をしたが、ジューシーで甘酸っぱく、特産品として申し分のない美味しさだ。
この日の最低気温は零下16度というかなりの冷え込みだったが、ハウスの中はじんわりと温かく、上着を着ていると汗ばみ、外気温との差でカメラのレンズが曇るほど。ハウスビニールは三重構造で、外側の2枚のビニールの間は、送風ファンで膨らませているという。
「暖房は日中は18度、夜間は10度に設定してありますが、日中の日射量や夜間の外の気温で変化します。ハウスの温度が高くなり過ぎないようにファンがあります。昼間は高温の時にはファンで換気をし、夜間は10度以下にならないように暖房をしています」と片澤さん。ハウス環境はコンピューターで管理し、温度や水、肥料、二酸化炭素の量を設定すると自動的に調整が行われているそうだ。
栽培は軌道に乗りつつあるが、冬いちごの栽培で比布町をいちごの産地として再活性化するにはビジネスとして成立をさせなくてはならない。そのためにも収穫量アップと利益を確実にあげることが求められる。
片澤さんは、「ハウスが1棟なので収穫量はまだ少なく、販売はナナプラザと比布スキー場のみ。収穫が多かった時には市場に出荷しています。規模拡大のためにさらに1、2棟ビニールハウスを設置し、利益を出せるようにしてから、町の生産者を巻き込んでいきたい」と意気込みを語る。
寒冷地での冬いちごの栽培例は少ないだけに、同法人がビジネスとして成功すれば、施設園芸のモデルケースとなるはずだ。