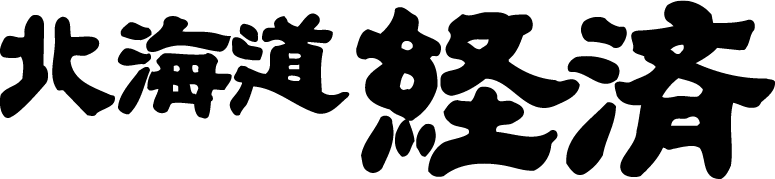当麻町の名産で、道内を代表する高級果物として知られる「でんすけすいか」が誕生し、30年の時を刻んだ。「これを食べたら、ほかのスイカはもう食べられない」と絶賛する消費者も少なくない。しかし一方で、今後に向けた課題もある。これまで試行錯誤を重ねてきた30年におよぶ苦闘の軌跡から、食のブランドの未来像が見えてくる──。
過去最悪の被害の後に
「でんすけすいか」の栽培は、水田の減反政策が進み、将来に不安を募らせていた当麻農協青年部の有志15人が1984年、一村一品運動の全国的な高まりを受け、当麻町の新たな特産品として取り組んだものだ。
 当麻町はその前年の10月6日、当時観測記録史上2番目に早い初雪に見舞われた。収穫直前の稲が、ほぼ100%なぎ倒されるという過去最悪の被害に、稲作農家は頭を抱えた。
当麻町はその前年の10月6日、当時観測記録史上2番目に早い初雪に見舞われた。収穫直前の稲が、ほぼ100%なぎ倒されるという過去最悪の被害に、稲作農家は頭を抱えた。
コメと並ぶ収入源となって、水田地帯を手助けする存在になってほしいとの祈りにも似た思いから、名づけられた名前が「でんすけ(田助)」だった。菊川健一町長は「逆境にあっても一隅を照らす光を求め、入植以来築いてきた先人たちのスピリットを継承するもの。その象徴が『でんすけすいか』」だという。
このネーミングは同時に、〝デン助〟の愛称で戦後の浅草喜劇界やテレビで一世を風靡したコメディアン、大宮敏充さんにもちなんでいる。
生産者でつくる「当麻町そ菜研究会でんすけ部会」の初代部会長を務めた瀬川守さんの強力なリーダーシップのもと、初年度の総栽培面積は2㌶で、総売上高は1660万円。10㌃あたりの売上げは、コメを上回る80万円以上にのぼった。
でんすけすいかは、深緑色の皮に重さ6~8㌔ほどの大玉。シャリシャリした食感と、すっきりとした甘みが特徴で、元々、海外向けに開発された品種「タヒチ」の一つとされる。
当時、真っ黒な皮のスイカは日本では見られなかったが、ヨーロッパや中近東では一般的。糖度や食味がそれほど良くなかったことから、種苗メーカーの「㈱サカタのタネ」が約10年かけて改良に取り組んだ。
でんすけ部会の現在の舟山賢治部会長は「当時の青年部員がタヒチと出会ってから今日までの経緯は、奇跡の連続だったように思える。誰も挑戦したことのない黒皮スイカの栽培をはじめ、赤と黒の段ボールに1玉出荷という発想には、志の高さを感じる」と振り返る。
出荷停止の挫折も経験
ただ、食のブランドを確立するまでの苦労は並大抵ではなかった。当初は露地で栽培したがなかなか実がならず、収穫しても品質が悪かった。近年の異常気象に伴う栽培環境の変化に対応し、病害虫も予防するため、安定した栽培管理ができるハウス栽培へと段階的に移行。01年からは、ハウス栽培の面積のほうが多くなった。
生産者が強く意識したのは、ブランドイメージの構築だった。栽培をスタートさせた時点から「糖度11%以上」の基準を守り、基準に達していないスイカは容赦なく除外。中には、持ち込んだ収穫物の半数以上が「不合格」と判定され、持って帰る生産農家もいた。
でんすけすいかは89年に商標登録され、90年には年間の販売高が1億円を達成。91年になると赤と黒の象徴的なデザインを施した特製の段ボール箱にスイカを詰めて高級感を演出したが、同年には着果した後の大雨の影響でスイカの肉質に異変が生じ、出荷の停止を余儀なくされるという不運にも見舞われた。
不意を突かれた格好になったが、生産農家たちは「あのシャリシャリ感は他の品種では出せない」として、引き続き栽培技術の向上を目指した。年に数回、栽培講習会や現地研修会を開くなどして、栽培方法の研究に心血を注いだ。
でんすけ部会ではこれと並行して、一元集荷や共同選別、共同販売など、生産から販売までの体制を確立。一連の取り組みは、95年の「第1回ホクレン夢大賞」や、96年に「第9回北の生活産業デザインコンペティション」パッケージ部門金賞の受賞にもつながった。
00年には、他産地に先がけて共同育苗施設を稼働させた。全国にも例のない取り組みとして、JAが当麻町の生産者にでんすけスイカの苗を供給するシステムを構築すると生産にも弾みがつき、04年にはでんすけすいかの年間の販売高が2億円を突破。こうした一連の取り組みが高く評価され、06年には「第35回日本農業賞」(集団組織の部)で大賞に輝く。
08年の初競りでは旭川で過去最高の65万円の高額取引を記録。12年には、町と農協からの支援を受け、最新の高性能光センサー選果システムを導入して設備をさらに充実させた。
昨年は、一玉2500円近い単価がつき、町は「でんすけ羊かん」の試験販売をスタート。同年夏には、海外進出を視野に、札幌の卸売業者「札幌丸果青果㈱」を通じて、台湾に向けて試験販売も行っている。
ブランドを守るために
しかし、昨年の売上高は1億6280万円にとどまった。栽培戸数の減少が主な要因だ。ピーク時の02年には、町内で67戸が21㌶作付けしていたが、昨年の栽培戸数は40戸で作付面積は15㌶に縮小している。
これらの背景には、ブランドを守るために固持してきた栽培基準の厳しさや、1個あたりの重さが平均で8㌔になるスイカの収穫作業の辛さなどがある。でんすけ栽培の労苦の手間を避け、比較的容易な野菜の栽培などに取り組む農家も出てきている。
当初から30年間、でんすけすいかを作り続けている生産農家は8軒。でんすけ部会の舟山部会長の信念はゆるぎない。「栽培当初からの夢やロマン、技術が引き継がれ、苦難のときも、統一された基準を必死に守り抜いた結果が、現在の礎になっている」
その一方で、部会では知名度アップにも取り組んでいる。昨夏には町内のイベント「蟠龍(ばんりゅう)まつり」で試食会を初めて実施。札幌市内の小学校から農村体験を受け入れているのも、「でんすけ」がもっと親しまれてほしいとの願いからだ。
糖度などの数値が基準を下回るスイカについても、捨ててしまうのではなく、加工品としての活用を模索。栽培に関するリスクを軽減し、できるだけ多くの農家に栽培してもらえるよう工夫をこらしていく。
今後の明るい材料として、「当麻農業未来創造チーム」(長谷川新会長)の存在がある。農業者や生花店、建設業者など異業種を含む30~40代の男女13人で昨年7月に発足。そのメンバーには、でんすけすいかの生産者も名を連ねている。
このチームでは、茨城県で水田100㌶を誇る大規模経営を手がける農業生産法人や、「直売所甲子園」で全国優勝を果たした同県の農産物直売所「みずほの村市場」を視察。でんすけすいかを台湾に試験輸出した昨夏の経験をもとに、東南アジアや中東などへの視察も検討している。16年春までに、新たな営農モデルを具体的にまとめ、全国に発信していくつもりだという。
デン助こと、大宮敏充さんは、浅草の演芸界で風刺のきいたコントを繰り広げ、「俺にデンとまかせておけ」との決まり文句で人気をさらった。でんすけすいかの未来も、生産者たちから「俺たちにデンとまかせておけ」と胸を張る声が聞こえてきそうだ。