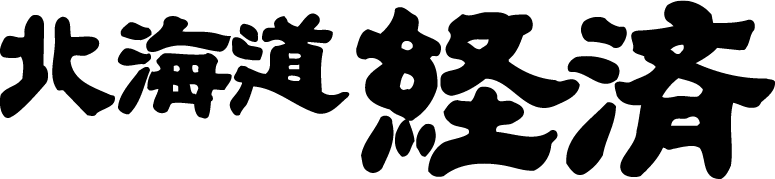旭川の天気がおかしい。大雨が降り、夏としては記録的な冷え込みを記録したかと思えば、7月後半は本州を思わせる暑さ。エアコンを設置していない家が珍しくないだけに、猛暑にぐったりしている人も多いはず。気になるのはこうした高温多雨の傾向が年ごとのデータだけでなく、長期的な傾向にも現れているということだ。今年よりも来年、来年よりも再来年と、旭川の天気は「熱く」なっていくのだろうか。
過去100年間の「7月」だけに注目
気象台のホームページにアクセスすれば、条件を指定して気象に関するさまざまな数値をダウンロードできる。本誌では1919年から2018年に旭川地方気象台で観測されたデータのうち、7月観測分だけに注目して、その変化の傾向を探った。
 まず、今年の7月初旬には台風から変わった温帯低気圧の影響で、短時間のうちに大量の雨が降り、旭川市内で発生した住宅地の冠水被害が全国ニュースで伝えられた。天人峡温泉では一時131人の観光客が足止めとなる事態も発生した。
まず、今年の7月初旬には台風から変わった温帯低気圧の影響で、短時間のうちに大量の雨が降り、旭川市内で発生した住宅地の冠水被害が全国ニュースで伝えられた。天人峡温泉では一時131人の観光客が足止めとなる事態も発生した。
旭川の348㍉という月間降水量は過去100年間の7月で1953年(418㍉)、2000年(382㍉)に続いて3番目の多さだった。これは宮前東にある現在の旭川気象台で観測した数値。東旭川瑞穂にあるアメダスによる観測では、2日9時から5日24時までで225㍉という数字が記録されている。
中旬をすぎると一転して暑い7月となった。25日からは7日間連続で最高気温が30度を突破。本州と九州を襲った台風に伴う気圧配置の関係で、この地域としては猛暑の34度超えも2日あった。ただ、月の前半は悪天候続きだったことから、7月を通してみた平均気温は21・3度。過去100年間では29番目と、顕著に暑かったとは言えない。ちなみに、今年7月5日に記録した一日の最高気温11・6度は、7月としては旭川地方気象台が観測を始めてから最も低かった。
10年間の平均値から長期傾向探ると
こうした気象データの変化は、年ごとの乱高下が激しい。折れ線グラフを描いてみると急な山や谷が連続し、長期的な傾向は読み取りにくい。そこで、過去10年間の平均値(2018年なら2009~2018年の7月だけの数値を足して10で割ったもの)を計算してみると、一定の傾向が読み取れた。まず過去10年間の7月の平均気温は、2008年の20・4度から2018年の21・39度へと、ほぼ「着実」に上昇し続けた。より長い目でみれば時代によって上昇したり下落したりしているものの、少なくとも1926年、つまり昭和初期から現在に至るまで21度を突破したことは一度もなかった。
ただし、ここで注意しなければならないのは、2004年8月と同年9月の観測の間で、観測地点が旭川東高付近から宮前東の合同庁舎に移転し、ベースが変わったということだ。周辺の環境の変化が測定される温度にも影響をもたらした可能性がある。観測地点移転の影響がなくなってからの5年間でもこの平均値は上昇を続けているが、今後も同様の傾向が続くかどうか、しばらく注目を続ける必要がありそうだ。
10年間のタイムスパンで見た平均値の変化がもっと顕著なのは降雨量だ。降雨量は気温よりもさらに1年ごとのばらつきが大きいが、それでも7月の雨が100㍉以上の年が増えているのは明らか。過去10年間の平均値も2018年には169㍉に達した。1974~1999年のいずれの年も、過去10年間をさかのぼった平均値は一貫して100㍉以下だったから、旭川で7月の雨がかなり増えたのは数字の上からも明らかだ。もはや「旭川の夏はそこそこ暑いが、雨が少ないので過ごしやすい」と自慢することはできなくなっている。
しかし、1974年よりも前に注目すれば、降雨量の長期的な変化にも「うねり」があることがわかる。10年間の平均値は、1960年代には概ね100㍉を上回っており、1962年は164㍉と、現在とほぼ同じ水準だった。見方を変えれば、70年代の中盤から90年代は比較的雨が少なかったとも言える。
「旭川のほうが暑い」と関西人ぼやく
7月末、旭川市内で開かれたある会合に参加するため、関西地区からやってきた人たちが異口同音に語っていたのは「涼しいと聞いていたのに、こっちのほうが暑いのではないか」との驚きだった。
プール、ビアホール、かき氷店など、猛暑を追い風に賑わうビジネスはある。しかし体の負担を考えれば、今年以上に暑い7月はもう来てほしくないというのが多くの市民に共通する思いだろう。本稿で指摘した「7月の高温多雨化」の傾向が、今後さらに進むのか、それともどこかで「低温少雨化」へと転じるのかに注目したい。
ちなみに、旭川地方気象台が観測を始めてからの7月で旭川が最も寒かった日は1890年7月7日で、その日の最低気温は1度だった。もしも旭川が同じ気候に戻れば、農業や産業、市民生活への打撃はともかく、猛暑に苦しむ日本全国の人々が涼を求めて旭川に殺到するのは確実だ。

この記事は月刊北海道経済2018年9月号に掲載されています。