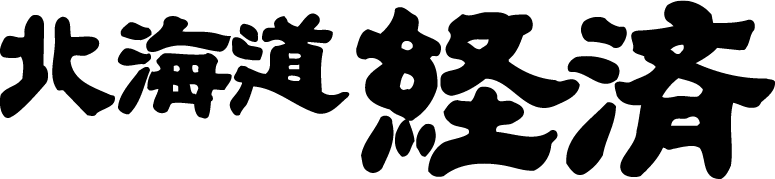内風呂の普及、少子化、燃料費の高騰…。数多くの問題に直面した銭湯が次々と廃業を余儀なくされている。旭川市内でもこの数年のうちに、いくつもの銭湯で釜の火が消えた。銭湯から客を奪っていたはずのスーパー銭湯やサウナ施設でさえ、コロナのあおりを受けて「退場」している。その一方で、ベテラン経営者から若手が経営を継承し、経営を継続する動きもある。みずほ湯改め虹の湯は、そのどちらでもない。以前からの経営者が多額の投資を行って全面的にリニューアル。銭湯やサウナの新しい楽しみ方を市民に提案し、従来とは違う客層を掘り起こした。

27歳から銭湯経営
旭川市の中心部から国道39号を北上し、コープさっぽろシーナ店の北側の交差点を右折して間もなく、虹の湯(旧みずほ湯)の緑の壁が見えてくる。創業は1964(昭和39)年。このころ、永山では水田が宅地として開発され、住宅と人口が急増していた。まだ内風呂がない住まいも多く、みずほ湯は住民のお風呂のニーズに応えた。ちなみに「みずほ」とはこの辺りの町内会の名前で、目の前には「みずほ公園」がある。
営業開始から7年後、創業者の弟が経営を引き継いだ。そして2000年に「3代目」となったのが、それまでの経営者兄弟と血縁関係のない佐野剛司さんだ。当時27歳で、アパレル店で徐々に責任のある役割を担うようになっていたが、高齢となった2代目が体調を崩し、銭湯の転売を考えていると聞いた。佐野さんは幼いころ別の銭湯に行った記憶があり、みずほ湯の古風な銭湯の雰囲気にも魅力を感じた。交渉を経て、金融機関から資金を借り入れてみずほ湯を手に入れた。
まだ独身だった佐野さんは、先代からの指導を受け、母親の助けを得ながらみずほ湯を経営。やがて佐野さんと結婚した妻の綾さんが戦力に加わった。地道な家族経営を続けてきたが、銭湯業界は「右肩下がり」が当たり前。風呂に入らない人はいないが、ほとんどは自宅でシャワーを浴びるか風呂に浸かる。市内のあちこちにできたスーパー銭湯も利用者を奪った。シャワーや風呂を併設したフィットネスジムも新たなライバルとなった。
1970年代の最盛期には129軒を数えた市内の銭湯の数は13軒まで激減。とはいえ、風呂なしのアパートなどに住み、クルマを持たない高齢者にとっては、みずほ湯などの銭湯が「ライフライン」としての役割を果たし続けてきた。
売上減が当たり前
銭湯は社会的にも重要な意味を持つ。みずほ湯からほど近い場所に、永山の市営団地がある。どの部屋にも風呂はついているが、市営団地で暮らす高齢者の中には、半世紀以上、銭湯に通っている人が少なくない。入浴のためだけではなく、外の空気に触れて、顔なじみの他の利用者と会話を交わすために足を運ぶ。
とはいえ、こうした昔からの利用者は徐々に減っていく。佐野さんは以前、金融機関に提出する資料の中で、売り上げが徐々に伸びていくとの計画を書き込み、同業の先輩から「銭湯は売上が減っていくものだよ」と指摘されたことがある。実際、みずほ湯の経営も次第にじり貧状態となっていった。
もう一つの問題が設備の老朽化。創業時から使い続けてきた釜に穴が開き、業者からは修理に数百万円がかかると告げられた。みずほ湯は釜の上にタンクなどが乗る特殊な構造だったために、修理が困難だった。建物も老朽化して水漏れが発生した。
いまから4年前、夫妻は決断を迫られた。買収時に行った借り入れは完済に近づいており、銭湯経営をあきらめて別の仕事を探すという選択肢もあったはずだが、今後の人生設計も考えたうえで、あえて新たに借金をして多額の設備投資を行い、銭湯をリニューアルする道を選んだ。サウナブームという追い風が吹いていたためだ。後継者不在で廃業に追い込まれる銭湯が多いが、夫妻がまだまだ働ける年齢であることも経営継続を後押しした。数年前から、行政が銭湯の設備整備のために用意している補助金のメニューを活用しつつ、タンク、濾過設備などを段階的に修理・更新した。
「いつ開くの?」
ただ、創業から初めての大規模なリニューアルだけに、必要な費用は何度も精査を繰り返しても1億円弱の規模に達した。政策金融公庫との交渉にも時間がかかったが、最終的にはゴーサインが出た。業者に「改築では確認申請が下りない。(費用がかさむ)新築しかない」と宣告されたこともあったが、関係者が知恵を持ち寄り、改築によるリニューアルが実現した。
今年1月1日から4月17日まで長期休業して建物と設備の工事を行った。この100日余りは、夫妻にとり銭湯がどれだけ親しまれているのか再確認する期間となった。なじみの客からは「再開を待っている」との声が相次いで寄せられ、現場の作業員たちは「いつ開くの?」と道行く人に繰り返し聞かれた。クルマを運転しない高齢者にとっては、永山にもう一つある銭湯までの移動が難しいという切実な事情もあった。
そして4月18日に待望のリニューアルオープン。同時に、長年掲げた「みずほ湯」の看板を下ろし、「虹の湯」に改称した。自分たちの銭湯である以上、自分たちで考えた名前にしたいとの思いが夫妻にはあった。「虹」は3人の子の名に関わりのあるキーワードだという。
リニューアルからもうすぐ2ヵ月。高齢者を中心とする長年の得意客に、新たな客層が加わった。若い家族、若い友人同士のグループ…。近くにある旭川市立大学の学生と思われる人たちも姿を見せるようになった。いずれもリニューアル前にはほとんど見なかった客層だ。
ロウリュサウナ追加
その大半が利用しているのがサウナ。以前も昔ながらの湯気式のサウナはあったが、新たに導入したフィンランド式オートロウリュサウナは、サウナ石に水をかけて水蒸気を発生させてサウナ室内の温度を高める。体感温度は十分だが、実際の温度は約80度前後とやや低めで、初心者からマニアまで幅広く楽しめるのが特徴。このロウリュサウナの登場が、日本のサウナ人口を一挙に拡大したといわれる。
虹の湯の入浴料は大人490円。サウナ利用は、虹の湯専用サウナマットを購入した場合、別途110円、レンタルマットを利用した場合160円がかかる。若い客層のほとんどがサウナを利用している。
こうした新たな客層は、日常のルーチンとしての入浴というよりは、サウナという娯楽のために虹の湯に足を運んでいる。このためドリンク、アイスクリームの売り上げも伸びた。若い層は遅くまで利用するため、いまは閉店時間ぎりぎりになっても人の姿がある。リニューアル前とは異なるスタイルの洗湯となった。
独自キャラ考案
設備の更新に合わせて、商売のスタイルも大きく変わった。入口で営業中であることを示す看板は、新たに考案したキャラクターの「虹ちゃん」。パンダをモチーフとする「サーちゃん」、「ウナちゃん」もそれぞれ男湯、女湯の入口に掲げられている。虹のマークをあしらったシャツ、タオル、サウナハット、キーホルダーなどオリジナルグッズも販売。インスタグラムを通じた情報発信にも力を入れる。いずれも「みずほ湯」時代には考えられなかった取り組みだ。
古くからの利用者も虹の湯にとっては大切なお客。長年通い続けた銭湯の変化に戸惑う人もいたが、いまは新旧の客層が湯舟に並んで浸かる。
虹の湯は現在、基本的に佐野夫妻が切り盛りし、剛司さんの母親が手伝っている。新しいしくみに順応するのに時間がかかることもあり、綾さんは「夜10時半に閉めて、清掃などを行って寝るのは2時ごろ。子供のため朝7時には起きている。毎日とても忙しい」と語るが、それでも利用者からの「気持ちよかった」の一言が大きな励みになっているという。
最盛期には現在のコンビニに匹敵する密度で、市内各地に点在していた銭湯。苦しい時代の先に吹いてきたサウナブームという追い風を受けて、新しい魅力を発信する銭湯が、他にも現れるはずだ。