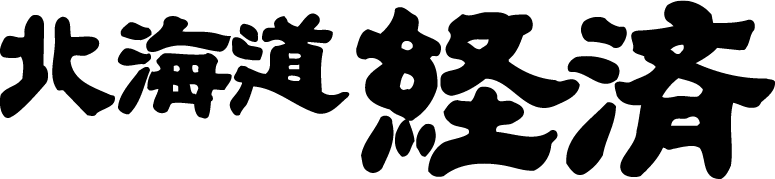すべての家庭から毎日排出され、下水管を通して下水処理センターに行きつく汚水。実はその中には、農業に不可欠な貴重な成分が含まれている。世界的な化学肥料への需要の増大、地政学的なリスクの高まりを背景に、いま政府が取り組むのが下水汚泥に含まれるリンなどの成分の活用。旭川市の汚泥についても昨年度、成分検査が行われ、上々の結果が出た。これをもとに旭川市では今後、汚泥を活用した肥料の開発などに取り組む考え。科学技術を活用したクリーンな「下肥」が近い将来、誕生するかもしれない。

農業支えた下肥
人が毎日体外に排泄する糞便は、いまでは「汚いもの」として忌み嫌われている。自分が出したものでさえ、目に触れるのは「流す」ボタンを押すまでのわずかな時間だけ。子育て中の家庭や医療・介護の現場を除けば、ほぼ視界の外に置かれている。
ほんの50年ほど前まで、状況はまったく違った。記者は1970年頃、水田から宅地に転換されて間もない豊岡地区(当時は「愛宕」)に住んでいたが、祖母が家の裏に作った自家菜園に、便槽から大型のひしゃくですくった下肥(肥料としての糞尿)をまいていた様子を鮮烈に覚えている。
ある時期まで、日本中がそうだった。徳川時代から百万都市だった江戸には下水道システムこそなかったが、下肥を屋敷や長屋から買い取り、農家に転売する商売があった。裕福な家から出る下肥は高く、貧乏長屋の下肥は買い叩かれるなど、ランク付けもされていたという。戦時中から戦後にかけては、東京など大都市圏でし尿の処理が困難になったこともあり、都市部から郊外の農村地帯に下肥を運ぶ専用列車が運行されていた。
しかし、戦後は下水道システムの発達、化学肥料の普及、寄生虫など下肥の健康面の不安が注目されたこと、そして何より人の排泄物を使って人の口に入るものを作るというイメージが嫌われ、下肥は次第に使われなくなった。
米国は輸出を禁止
旭川市の下水処理を一手に引き受けている忠和の下水処理センター。下水管を通して送り込まれる汚水は微生物による分解や脱水処理を経て汚泥となり、さらに焼却される。年間約1500トンの灰が出るが、そのうち600トンはセメント材料となり、残りは江丹別中園の廃棄物処理場に埋め立てられる。セメント材料としての再活用は、旭川市が引き取りのコストを一部負担しており、収益だけみれば商売としては成り立たない。
下水処理センターには下水資源多目的活用センター(通称=バナナ館)が併設されている。下水処理で発生するバイオガスを燃やして暖房に活用し、バナナやパイナップルといった熱帯地域の植物を育てている。下水汚泥から生み出されるのは、セメント材料の灰とバナナくらいのもの。それが長い間の常識だった。
この施設が、重要な「資源」を生み出す可能性が出てきた。現代の農業に欠かせないリンを下水処理施設の汚泥から取り出す構想が、いま政府によって進められている。
2023年度、国土交通省が行ったのは、全国108ヵ所の下水処理場での、脱水汚泥、汚泥の燃焼灰などに含まれる肥料成分、重金属の分析。同時に、下水汚泥資源の肥料利用を検討する自治体への支援も行った。
農業を支える三大成分が窒素、リン、そしてカリウム。このうち窒素は空気の5分の4を占める窒素分子からアンモニアを製造する「ハーバー・ボッシュ法」という手法を使って、エネルギーさえ投じれば無限に生産できる。一方、リンとカリウムは鉱石から生産しなければならない。
日本にはリン鉱山がなく、リン鉱石は100%を輸入に頼っている。輸入量を国別でみれば、中国が最多で、これにモロッコ、南アフリカ、ヨルダンなどが続く。しかし、リン鉱石は農業に欠かせない物資であることから、政治的な思惑で輸出が制限されることがある。以前、日本にとり最大の輸入先だったアメリカは1996年に輸出を事実上禁止した。代わって最大の輸入先となった中国も、2008年にリン製品に高い輸出関税をかけた。2019年には急激なリン高騰が発生している。日本のリン鉱石輸入量は減少傾向にあるものの、世界的には食料増産でリン鉱石への需要が増しており、今後、リン鉱石、さらにはリン肥料の確保が難しくなる恐れもある。食料安全保障の観点からは、リン資源の確保が重要な課題。これまで大半が捨てられていた下水処理施設の汚泥に含まれるリン成分注目が集まっている背景にはこうした状況がある。
成分検査は「合格」
推計によれば、下水道にはリン鉱石として輸入されるリンの約4~5割に相当するリンが流入しているものの、有効利用されている割合は約1割に過ぎない。国土交通省は2008年に「下水・下水汚泥からのリン回収・活用に関する検討会」を設置し、専門家が品質管理、コストなどについて検討を重ねてきた。現在は2030年までに下水汚泥資源の肥料としての使用量を倍増するとの目標を掲げる。実現に向けて行われたのが、全国の下水処理場から排出される汚泥の状況調査だ。
旭川市も対象自治体の一つに選ばれ、下水処理センターから送られたサンプルについて検査が行われた。調査結果は、今後に期待ができる内容だった。りん酸全量含有率は春から冬にかけて4・80%、4・91%、4・79%、4・04%。基準とされる公定規格「菌体りん酸肥料」への登録条件である、1・0%以上を軽々とクリアーした。こうした傾向は、検査の行われたほかの施設でもほぼ同じ状況だった。
リンが含まれているとしても、他に人体に有害な成分が含まれていれば汚泥の活用は困難だが、ヒ素、カドミウム、水銀、鉛など重金属の比率は基準値を大幅に下回り、安全なレベルであることが確かめられた。少数の下水処理場では、これらの物質が基準値を上回っていた。
ただし、現状は汚泥からのリン回収の可能性が示されたに過ぎず、事業として本格化するにはユーザーとなる農家からの意見聴取、農薬の試作、試験栽培、農薬としての登録などいくつものハードルを超えなければならない。このため国交省は成分の検査と並行して「下水汚泥資源の肥料利用を促進するための大規模案件形成支援事業」も23年度に実施。旭川市も採択された。
旭川市下水処理センターでは、国から派遣されるコーディネーターの助言を得ながら、今後の肥料化に向けたプランを練った。それによれば、旭川市農政部、市農業センター、上川農試などの研究機関、肥料メーカー、農協、地域の農家などと協議しながら流通経路の検討、経済性の検討を経て、肥料の登録、試作を行う。同センターは、まずはバナナ館で使いたいとの考えを示す。
食料安全保障
日本の食料自給率はカロリーベースで4割を下回っている。これは、単純に国内で消費される食料のうちどれだけが国内の田や畑などで生産されたかを示す数値。現代の農業に欠かせない肥料、飼料も計算に加えれば、実質的な自給率はもっと下がる。食料の輸入に問題がなくても、肥料・飼料の輸入が滞れば、日本人の食卓に大きな影響を及ぼすということだ。なかでも重要な物資であるリンを安定的に確保するためにも、下水汚泥からのリン肥料獲得は、食料安全保障の角度から見て大きな意味を持つ。
「有機野菜」の4文字は多くの消費者をひきつけるのに、その究極とも言える下肥の活用は進まない。清潔感が重視される食材販売の現場にとり、下肥のマイナスイメージがあまりに大きいのは事実。一方で、化学的なプロセスを経て肥料化したものを用いる農業なら、消費者にとってもハードルは低いはずだ。いまはもっぱら汚水を処理している下水処理センターが、いつか農業に役立つ肥料を生産する日が来るかどうかに注目したい。