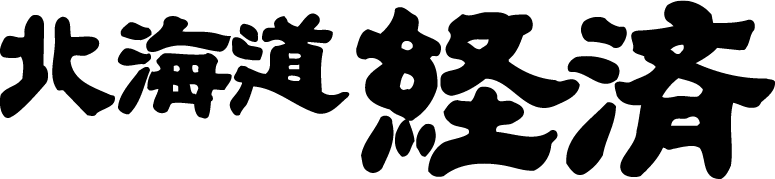石狩川・忠別川・美瑛川など大小合わせて130を超える河川が市街地を流れる旭川市は、川のまちであると同時に橋のまちでもある。やわらかなアーチが印象的な旭橋を筆頭に市内には760もの橋梁がある。造形美を競演するかのような橋梁に衆目が集まる一方で、老いて役目を終えたその橋は人目にふれることもなく今もひっそりとたたずむ。旭川最古の橋ともされる観魚橋(旭川市神居町春志内)だ。「アーチ型の煉瓦橋脚は美しく、歴史を感じる貴重な遺構です」。旭川の歴史的建物の保存を考える会副会長の竹田完二さんは、観魚橋が多くの人たちの目にふれ、末永く残ってくれることを願っている。

開拓史を見てきた
国道12号を旭川市街から深川方面に車を走らせ、台場を抜けしばらくすると「観魚橋」の橋名標識が目に飛び込む。だが、これではない。進行方向右手奥にもう一つ橋があり、さらにもう一つ奥にたたずむのが旭川最古の橋? とされる観魚橋だ。
国道を支えるのが現役の三代目で、脇の旧国道で今はサイクリングロードにあるのが二代目、初代と並ぶ。三つの橋梁が並ぶさまは壮観だ。
『断章 旭川アイヌ語 地名研究』(高橋基)によると、1890(明治23)年に上川道路を通り調査した永田方正は、次のように地名解をしている。オン子ナイ川(大川)─《支流中の大川なり。橋あり、初め思案橋と名(づ)け、後ち観魚橋と名(つ)く。然(しか)れども魚は只鱒あるのみ》。オン子ナイ川の現在の公式河川名は神居第一線川である。
1890年に永田方正が記録した中に「観魚橋」の橋名があることから、134年前には存在していたことになる。現在の国道12号の観魚橋は1991年から使われている。旧国道で現サイクリングロードの観魚橋は1959年に架けられた記録が残る。
「観魚橋は上川道路に架けられたものと思われます」。竹田さんは、旭川・上川開拓の歴史をつぶさに見てきた歴史的建造物との認識を示す。
上川道路(札幌─旭川間)は大変な思いをして造られた。架けられた観魚橋もそうであったろう。
囚人道路とも呼称
上川道路は、ときに囚人道路とも呼ばれた。北海道庁長官が上川道路の開削を命じて、樺戸集治監(現・月形町)の囚人たちを動員し、人力で1889年ごろ全線開通したとされる。永田方正の調査記録や竹田さんの考察を踏まえれば、上川道路造成の際、観魚橋は架けられた、と見るのは不自然ではない。囚人たちも煉瓦を運び、積み上げたかもしれない。
三代目は現国道として、二代目はサイクリングロードとして現役だが、上川道路だったと推察される初代の観魚橋は、ある意味、何の役にも立たずにそこに在る。幅員5メートル、長さ17メートルほど。橋上には草木が生い茂る。
「河原を下りて煉瓦の橋脚を見ると、かなり大幅な修復を受けていることが分かりました」。今春、竹田さんは現地を探索し、煉瓦橋脚を囲むようにコンクリートで補強し、橋げたもコンクリートが施されているのを現認した。「(橋げたの補修の仕方は)これは、明らかに煉瓦の橋脚とは時代を異にするもので、つまり4代にわたる観魚橋の痕跡があることになります」
瀟洒なイギリス積
「煉瓦橋脚は、『イギリス積』という積み方がされています。これは明治20年以降に見られる積み方で、強度が強く橋脚のようなものは、よくこの積み方をされています」(竹田さん)
さらに竹田さんは、「旭川まで鉄道が通ったのが明治31年で、この時に鉄道関係施設のトンネルや鉄橋などの建設に大量の煉瓦が使われました。観魚橋の橋脚は、このころのものと想像できますが、年代の特定は難しいです」。当時、観魚橋近くの台場に煉瓦工場があったことから、こちらで調達したとも推察できる。
「煉瓦橋脚に対して両側の橋台部分がコンクリート製であることも観魚橋が改修されていることを物語っています」
観魚橋には、目を引く特徴が幾つかある、と竹田さんは言う。「橋脚の中央部にアーチ型の穴があいています。力学的に力のかからない部分である中間部を抜いても影響が少ないので材料を減らすために穴をあけたのか、装飾的な意味を持たせるためにあけたのかは分かりません」。素人ながら、記者はシンプルなアーチ型の空洞が、煉瓦素材が醸す特有の重厚さを緩和して洒落ている、と感じる。
「アーチ部の頂上には要石があります。観魚橋の要石は比較的大きくしっかりと装飾の意味を持った物が使われています」(竹田さん)。当時の設計者、あるいは現場の職人が遊び心で要石を意匠したのだろうか? いずれにしても当時の鷹揚・闊達の精神がにじむ。
もう一つ大きな特徴がある、と竹田さんは指摘する。「橋脚上部に凹凸の出っ張った石が並んでいます。これが珍しい。国内で最も有名な煉瓦アーチ橋である群馬県の碓井第三橋梁にも突起があります。この突起を利用してさらに上部のアーチ型煉瓦を積み上げています。ですから、観魚橋の突起も同様ならば、ひょっとしたらコンクリートによる改修前は煉瓦アーチ橋だった可能性もあります」。上部の突起物と要石の装飾的な味わい、アーチ構造─。観魚橋は意匠を凝らしたすてき建造物だった。
拡幅工事でどうなる
現在、旭川開発建設部(国交省)は、国道12号・神居古潭─神居町春志内間の道路改良(拡幅など)工事を進めている。工事に伴い初代の観魚橋が撤去される可能性はあるのだろうか? 幸い、旭川開建は「現時点で観魚橋に手をつける計画はない」と説明する。
「観魚橋が残っている理由がいろいろと考えられます。単に取り壊し費用がかかるという理由のほかに、そこに歴史を感じ、思いをはせる人たちを感じます。貴重な遺構を壊すのは惜しい、という思いが、この観魚橋を存続させているのかもしれません」(竹田さん)。
経済効率的に何の役にも立たない無用の長物が未だそこにある。「『これはいいもんだぞ!』『もったいない』と道路改良・改修をした当時の工事関係者の人たちが、そっとしてきたんじゃないかと思います」(竹田さん)
歴史を感じさせ、デザイン的にも価値のある観魚橋にスポットライトをあてる方法はないのか。「道路改良する際、観魚橋に市民らが見に行きやすいよう整備してほしいですね。少し整備すれば立派な観光資源になる歴史遺構が観魚橋なのです」(竹田さん)
歴史を刻んだ建造物を愛する旭川市内の70代男性は、「上川道路は当初は幅2メートルくらいの刈り分け道路だったという記録と観魚橋は符合する。旭川最初の橋の可能性は高く歴史的価値も高い。そのまま残してほしい」と話し、こう続けた。「かつて屯田兵として永山や東旭川に入植してきた家族一行も、荷物を担いでこの橋を渡ったのかもしれないと思うと、その情景が浮かんでしみじみしてしまう」
国内最後の内戦・西南戦争から十数年後、それぞれが、それぞれの修羅を抱え、大地の開拓とともに自らの生を切り拓こうと、数多(あまた)の屯田兵・開拓民が渡った観魚橋は〝明日に架ける橋〟でもあったろう。今、静かにたたずむ観魚橋をどう未来に架けるのか、私たちが問われている。