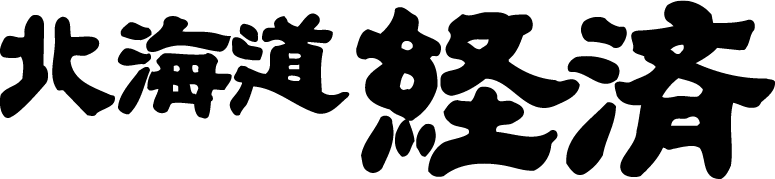東旭川旭正地区に住む農家のお母さんたちが手がける「ゆきわみそ」は、旭川産の大豆を煉瓦造りのかまどで炊き、大きな木樽でじっくりと熟成させる。昔ながらの製法で丁寧につくる味噌は、旭川市民だけではなく全国にもファンがいるほどの人気だ。半世紀にわたって継承されてきた味噌づくりを取材した。

体への優しさ
旭川市と旭岳を結ぶ道道1160号線沿いにゆきわみその店舗と工場がある。店舗名は「未っちゃん家(ち)」。ログハウス風の店舗に入ると、冷蔵ケースがあり、中にはカップや袋に入った味噌がびっしりと並んでいる。店舗は無人のため、買物客は店内のブザーを押す。そうすると隣接する工場からスタッフが現れて接客をするというシステムだ。旭岳に向かうドライブコースということもあり、平日でも買物客が途切れない人気の店。
創業は1976年。食生活が大きく変化し、農村地帯の旭正二地区でも自家製味噌を作る家庭が減っていた時代だった。野菜や米を生産していた地区の農家の女性たちの間で「添加物の入っていない体に優しい食べ物を家族に食べさせたい」という声が高まった。どんな食品が良いのか話し合った結果、転作で栽培した大豆を使い、味噌づくりに取り組むこととなった。
当時のメンバーは13人。各家庭で作っていた味噌を持ち寄って味見をし、一番評判の良かったレシピを使うことに決めた。町内の会館に集り、米農家の光沢房子さんが中心となって手作りの味噌づくりが始まった。
当初は家庭で味わうためのものだったが、余った味噌を朝市や農業祭りで販売したり、地域の人たちに味見用に提供するうちに、「味噌を分けて欲しい」という希望が増えていった。
味噌づくりを始めて10年目となる86年、地域の学校給食の古い釜や食器消毒機が払い下げられることとなり、仲間の間で「せっかくなので味噌の加工場を作ろう」という機運が高まった。工事現場で使われていた古いプレハブ住宅を自分たちの手で改築し、保健所から販売加工の許可が下りたことでメンバーの気持ちが一層高まった。外注していた麹づくりも自分たちで行えるように、食器消毒機を改造して麹製造機も製造した。1回に1俵半(90キログラム)の麹を作れるようになり、これまで毎月10万円かかっていた麹の加工費も削減することができた。
工場の本格稼働は翌年の87年。ゆきわみそというネーミングが生まれたのもこの年で、北海道の「雪」と仲間の「輪」にちなんで名付けた。
煉瓦造りのかまど
ゆきわみその特徴は、素材と製法へのこだわりだ。旭川で栽培された大豆と米(きらら397)を使用し、水は大雪山の伏流水を利用する。大豆は煉瓦造りのかまどで炊き、創業時に初代メンバーが各家庭から持ち寄った大きな木樽で味噌を2年間かけて熟成させる。長いものでは17年ほど樽の中で寝かせているものもあるという。
2代目で、みそソムリエの資格を持つ髙橋由味子さん(72)の案内で、味噌づくりを見学させてもらった。髙橋さんは、創業者の光沢さんの長女で、2006年に代表に就いた。母親の房子さんと一緒に店を切り盛りしていた妹の未知子さんがこの年に他界し、その意志を継いだのだという。工場の隣に店舗を開設し、未知子さんのことを多くの人に覚えていて欲しい、という思いで店の名前は「未っちゃん家」と名付けた。
現在のメンバーは、髙橋さんと望月素代さん、髙橋さんの義理の妹である光沢頼子さん。高齢化で造り手の人数は減っているが、望月さんは味噌づくり歴12年、光沢さんに至っては30年というベテランなので、少ない人数でも味噌づくりには支障がないようだ。
味噌づくりは木曜の麹づくりから始まる。髙橋さんの説明では、味噌の出来栄えは麹によって左右され、米にコウジ菌が繁殖し、白い花が咲くように見える「花が咲く」といわれる状態になると、甘味のある味噌に仕上がるという。
煉瓦造りのかまどにセイロを乗せ、米を蒸す。蒸し上がった米は、ゴザを敷いたテーブルの上に広げて冷まし、ガーゼの中に種麹を入れて、米に付ける。それから手で丁寧に混ぜる作業が行われる。ゴザを敷くのは、米に傷をつけることで麹菌が米に入りやすくするためだという。木製のオリに詰め、33度の温度に設定された麹製造機に入れて、3日間ほど寝かせる。
本格的な味噌づくりをするのが、木曜日に仕込んだ麹が出来上がる日曜日。午前中に、煉瓦づくりのカマドに薪をくべて、大豆を炊くところから作業が始まる。
ひと釜で炊ける大豆は26キログラム。午前9時から3、4時間かけて火加減を調整しながらの作業。茹で上がりに近づくと、工場内は豆の甘い香りでいっぱいになる。
小さな鍋を使って大豆をざるに上げるのは光沢さん。望月さんが茹で上がった大豆を専用の機械ですりつぶし、髙橋代表と一緒に米麹と塩を手早く混ぜ合わせる。それを木樽に詰めて作業は終了する。木樽に詰める作業を担当した望月さんは「『美味しくなーれ』と願いを込めながら木樽に詰めています」と笑顔で話す。
仕込みを終えた髙橋代表もホッとした様子で、「お客様から『美味しい』と言ってもらえることが味噌づくりの醍醐味です。店舗では量り売りもしていますが、お客様が持参された容器で、何度も買いに来て下さる方も多く、うちの味噌を食べてくれているんだなと嬉しい気持ちになります」と話してくれた。
後継者が決定
3人の造り手が丹精込めて作った味噌は、未っちゃん家をはじめ市内のスーパーやJAあさひかわの直売所あさがおで販売されている。
ギフトとして贈られたゆきわみその味を気に入って自家用に購入するようになった人も多く、全国にユーザーの輪が広がっている。
一番人気が高い味噌は、枝豆用の青大豆を使用したもの。クセがなく、口当たりの良い味噌で、リピーターの多い看板商品となっている。黒大豆を使用した味噌は、豆自体の旨みが強く、豚汁やあげなどの具材と相性が良いそうだ。
取材中に来店した女性に話を聞いた。以前からゆきわみそに関心があったという女性は、今冬から購入をしているという。「車でお店の前を通るたびに気になっていました。2ヵ月くらいで使い切ってしまいます。やさしく深みのある味がして、とても美味しいです」と話してくれた。
ゆきわみそは今年で創業48年という長い歴史を持ち、半世紀にわたり、農家のお母さんやお嫁さんたちが大切に継承してきた。
造り手の3人はとても元気だが、後継者がいるかどうか気になるところだ。
髙橋さんに尋ねると、「頼子さんと、私の甥っ子のお嫁さんが味噌づくりを継いでくれることが決まっていますので心強いです。心配してくれるお客様も多く、お話をすると『良かった』と喜ばれます」と笑顔を見せる。
家族の健康を願い、東旭川の農家のお母さんたちが始めた手作り味噌。その輪は全国に広がり、多くの人に愛され食されている。旭川が誇るゆきわみそが今後も長く継承されていくことを願いたい。