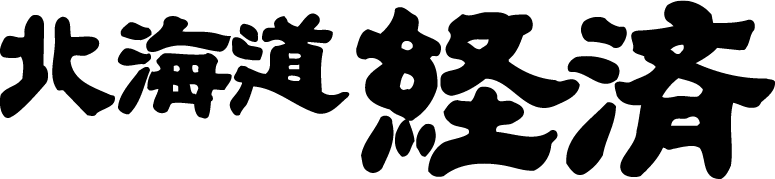昭和の初めに、新たな時代の刺繍としての地位を確立した「文化刺繍」。その魅力に惹かれ、長年、制作の担い手として作品を展示発表し好評を得てきた旭川市の佐々木幸子さん(83)。今や文化芸術界の〝絶滅危惧種〟ともされる希少な存在になりつつあるジャンルの一つだが、「糸の油絵」と呼ばれる文化刺繍は、質感とともに、独特な世界観を紡ぎ出す。その醍醐味を積極的に追求してきた佐々木さんの多彩な作品にスポットを当ててみる。
一針一針ごと、味な〝糸加減〟でグラデーション
 被り物をした異国情緒漂う女性の横顔を描いた聖画「祈り」。敬虔そうな彼女の首元には十字架のペンダントがさりげなく光っている。その画面は金ラメ入りの金紗織地で覆われ、ひときわ上質感を醸し出している。18色の糸を用いて詰めて刺しながら、全体として立体的に表現したという。
被り物をした異国情緒漂う女性の横顔を描いた聖画「祈り」。敬虔そうな彼女の首元には十字架のペンダントがさりげなく光っている。その画面は金ラメ入りの金紗織地で覆われ、ひときわ上質感を醸し出している。18色の糸を用いて詰めて刺しながら、全体として立体的に表現したという。
「自分の顔と長く付き合っているから、自分に似る?」と美術仲間から冷やかされるが、確かに作者自身の心のありようは作品に映し出される。そのせいか、楚々とした作者のたたずまいが女性モデルの表情に投影されている。かといって作業を振り返ると「目と口に工夫をした。怖い目にならないよう、あまり口を大きくしないように一針一針、神経を使いました」。
瞳には茶色を施したが、「多く糸を使ってもダメだし、少なくとも微妙」。目元に用いたブルーにも「たくさん糸を入れると、隈になっちゃうから」と佐々木さんならではの味な〝糸加減〟でグラデーションを表現している。口にはサーモンピンク、唇の横と下に金系、頬はピンク、頭巾にはレンガ系の色合いの糸を使った。
講師の資格を取得する際に挑んだ作品で「糸のつながりが難しかった」。顔は、先に刺した色の中へ次の色を割り込ませながら刺す「ボカシ繍」と呼ばれる技法を駆使。鼻から文化刺繍針で糸を刺し始め、しだいに下部へ針を進めた。「繊細な仕事。唇の出来しだいで年齢が出るし、すっきりしたものこそ粗が出る。人物画よりも、かえって風景のほうが誤魔化しがきく」。
そう本音をのぞかせる佐々木さんだが、作品を収める額の重要性も指摘。額は人でいえば、ヘアースタイルに当たるそうだ。
これに対し「高千穂峡」は50代後半の作品。立体と遠近法を意識した力作で、遠くにあるものから先に糸を刺し、岩は左側から刺し、次に葉っぱ、力強い滝は最後に手がけ、白い流れは厚く糸を重ねて刺していった。全体的には金ラメ地を生かし、奥行きを出しながら、光が反射するニュアンスを取り込み、水面の濃淡にもひと工夫。「単なる写実ではない、古典的な表現に努めた」と佐々木さん。
ヨーロッパを起源に持つ文化に日本の美意識紡ぐ
ヨーロッパで20世紀初頭に誕生した文化刺繍。これが日本にもたらされたのは1928(昭和3)年、チェコスロバキアで行われた第6回国際美術教育会議に、日本代表として出席した美術教育家で手工芸家の岡登貞治が、そのとき催された「美術工芸の用具材料展」から材料等を持ち帰ったことが、きっかけだという。
それでも当初日本では、ほとんど浸透しなかった。糸を使って絵画をつくる技法を日本で初めて成功させたのが、後に佐々木さんが講師と師範の資格を取得することになる「松鳩文化刺繍」。そして日本における文化刺繍が一定の地位を確立できた時期は、文化刺繍に関連した書物の著者でもある藤崎豊治らが改良を加えた30~35年にかけてだ。ちなみに、新しい時代の刺繍という意味で「文化刺繍」と名づけられた。
45~55年に至るまで最も研究が進み、裏刺しの技法を応用した起毛法が考案され、より精緻な刺繍制作が可能になった。虎をモチーフに日本画風に仕上げる作品も生まれ〝糸の油絵〟と呼ばれるようになり、ヨーロッパを起源に持つ文化刺繍が日本でも徐々に普及する。
50~60年にかけては刺繍しやすい生地を生産し、糸の多色染色も行われた。その後、糸はリリアン(手芸用のヒモ)をほぐしたものを用いて、用具が単純で技法も比較的難しくないため、一般の愛好者にも喜ばれた。さらには家紋や山水画が発表されると、掛け軸も市販されるようになる。
こうした変遷をたどりながらも、現在は絶滅危惧種的に希少価値の高い文化となりつつある日本の文化刺繍。道内でも風前の灯火となっているが、その魅力は作り手たちが最も実感してきた。手間のかかる作業ではあるが、基本技法の「ランニング刺し」や、糸と糸を割り込ませる「ボカシ刺し」、斜めに刺す「コード刺し」を通じ紡がれていく作品には、質感とともに独特な味わいと趣がある。
白と黒のモノトーンを基調とする山水、幸運を招く「開運招福の赤富士」、日本人ならではの美意識〝侘び寂び〟に裏付けられた家紋や各種縁起物。毛立ての手法で仕上げた虎をモチーフにした作品。「夕景」「牡丹」「紫陽花」といった日本の風景を題材にした佳作にも佐々木さんの創作に費やしてきた情熱をうかがい知ることができる。

この記事は月刊北海道経済2020年07月号に掲載されています。