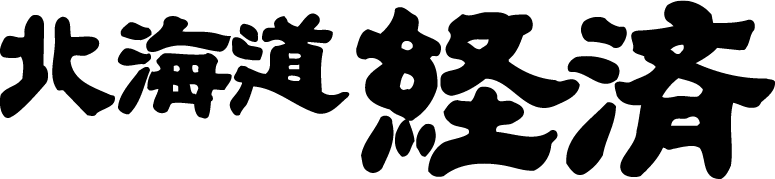木を紙のように薄く削った「経木」。大和時代から食品包装材として使われ、経木で食品を包むのが当たり前だった時代もあるが、今では発泡スチロール製トレイやビニール袋にすっかり取って代わられてしまった。しかし最近、通気性や殺菌性にすぐれ、環境に優しい経木が再び注目を集めている。道内に残る3つの工場のうちの一つ、旭川市の「野崎経木工場」(東7条6丁目)を訪ねた。
伝統守り続ける親子
新旭川駅に程近い野崎経木工場。敷地内には道内産シナノキの丸太が積み上げられている。丸太をチェーンソーで製品よりやや大きめのサイズにカット。1階の作業場に移して丸ノコで規格の寸法に切り落とし、3面だけカンナ掛けをして四角い木の塊「駒」をつくる。
この駒を大きな鰹ぶし削り機のような年季の入った経木製造機(1963年製)にかけて薄く削ると、紙のように機械から次々に出てくるのが経木だ。厚さは0・2~0・3㍉ほど。工場内は木の香りに満ちている。
工場の2階では束状の経木が吊るされ、扇風機の風を受け乾かされている。このプラスチック包装全盛の時代、経木は「時代遅れ」と考えられがちだが、野崎敏雄さん(81)と猛さん(49)親子が伝統を守り続けている。
野崎経木工場は1963(昭和38)年に創業。家内制手工業のスタイルを守りながら年間を通じて月に10立方㍍から12・3立方㍍を製造している。規格には鮮魚店の値札などに用いられる3寸サイズのものから、おにぎりの包装に使う4寸、精肉店ほか鮮魚店で鮭の半身などを載せる5寸、菓子を作る過程で使われる6寸サイズなどがある。1尺3寸の長さで幅が5寸の規格は納豆を包むのに用いられる。
販路は旭川市内にある鮮魚店をはじめ、釧路や北見、函館などの道内各地、秋田県を主体に東北ほか、博多を中心とする九州方面など。「ここ30年来、値段は変わっていない」と敏雄さん。道内で経木を製造している工場は、野木経木工場のほか、美瑛と丸瀬布にしかないという。
繰り返し使える記録媒体
経木が最も脚光を浴びたのは明治期。1904(明治37)年に農商務大臣により重要生産品に指定され、経木で作ったマッチ箱や経木真田(帽子の材料)、経木織物は輸出産品として生糸や絹などと肩を並べる存在となり、全国各地に工場があった。紙のように薄く木を削ることができる技術を備えているのは日本だけだ。
「経木」と呼ばれるようになったのは、元々はお経を書き込んでいたため。削れば書き直しが何度もできるため、紙が普及する前まで広く記録媒体として用いられた。
「新旭川市史」によると、経木は、包装材料としてプラスチック製品が使われるようになる最近まで広く用いられていた。折敷、曲物、マッチ、人造竹皮、経木皿などに利用。折箱等に使用されるものを「厚経木」、魚類や菓子の包装に使われるものを「薄経木」と呼んだ。
上川管内では1905年、道庁が農家の副業として経木製造業を奨励。経木の主な用途は、食品を直接包む紙状の薄板(北海道では「薄皮」)と折箱の材料とする厚経木に大別できる。経木製造の原料として、本州ではヒノキなどが用いられたが、道内の開拓で薄経木の原料にはシナノキの木が適当であることがわかり、明治30年代半ばに「シナ経木」が生まれた。次いで色が白く材質が柔軟かつ安価なエゾマツが厚経木の原料として最適とされ、「結局本道が経木の主産地となった」と市史には記されている。
経木の原木がシナノキやエゾマツで、需要は都市から農漁村市街地に至るまで広かったことから、全道各地に製造工場が登場。大雪山系に接して原木の豊富な上川地方や旭川は主産地の一つとされ、「昭和十年ころには、恐らく全道最大の経木産地に成長していたと推察される」(新旭川市史)。
1967(昭和42)年に発行された「全国経木製造業者名簿」によれば、当時、道内には127業者が登載され、旭川地区には22業者が存在。旭川で生産された経木は市内での消費はもとより、道内および小樽の問屋を通じて小樽港経由で本州の消費地に移出されていた。
単なる懐古主義でなく
現在、この経木が見直されているのは、単なる懐古主義からではない。食材の鮮度が落ちる原因として、表面の水気による細菌の繁殖が挙げられるが、経木は表面の水気を吸うので繁殖を抑制する。吸水シートとは異なり、水気を吸い過ぎないため刺身がパサついたりしない。木の殺菌成分によって、味と鮮度を保つことができるのもメリット。魚の切り身は経木で数時間はさんでおけば、臭みも消える。経木には吸水作用、調湿作用があるため、ごはんがオヒツに入れたようにおいしくなり海苔が手につかない。
納豆、揚げ物、まんじゅう、肉まん、惣菜など、さまざまな料理の敷物や包装材料として使われる守備範囲の広さも経木の魅力だ。適当なサイズに切って使えること、使用後は焼却したり、堆肥化することができ、環境に優しいことも時代によくマッチしている。
経木の素材は主にアカマツとシナノキ。宮城県を境にして南がアカマツ、北はシナノキが用いられる。シナノキにアカマツほどの香りはないが、「昔はサンマも味噌も佃煮もこれで包み、おにぎりも握ったままの感じでおいしかった」と懐かしむ市民もいる。
野崎猛さんの小学生のころの思い出といえば、スーパーでスパゲッティや惣菜の量り売りをしていた場面。個人経営の豆腐店で経木が使われていたことも印象に強く残っている。そんな野崎少年は、小学校低学年から自宅の工場に出入りしては、父親の敏雄さんたちの箱詰め作業を手伝っていた。
今でも、秋から暮れにかけては普段の倍ぐらい生産しているが、全体的には減産の一途。猛さんは「かつては食品を包むことがメインだったが、対面販売が少なくなってきていることもあり今後、これまでとは違う発想で取り組んでいく必要がある。どういう経木の使い方があるのか探っていきたい」と話す。

この記事は月刊北海道経済2016年07月号に掲載されています。