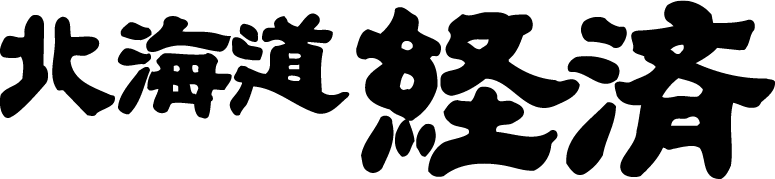本誌創刊50周年企画第2弾は「倒産」。地域社会の縮図とも言える企業倒産は、経営者や従業員、取引先にとどまらず、市民生活の中にも暗い影を落とす。同情すべき倒産も多いが、それを鑑みたとしても「倒産は罪悪」であることに変わりはない。本誌はこれまで企業倒産がもたらす社会的影響の大きさ、悪質さを基準として記事化してきた。それらの中から特に次代に伝えておきたい倒産劇を集め、旭川半世紀を振り返ってみる。
〝日本の松岡〟破綻 過大投資、負債30億
1970(昭和45)年の30億円は、当時と現在の企業物価指数(企業同士の取引価格)で換算すると、およそ2倍の60億円。これほどの負債額を抱えた倒産は、それ以降の旭川でも数少ない。同年12月14日に会社更生法の適用を申請した松岡木材産業㈱(旭川市近文19丁目、松岡一隆社長、資本金1億5千万円)の倒産は、道内外の取引先、金融機関、そして約360人の社員、その家族らを震撼させた。
同社は明治40年創業の老舗。初代の松岡源之助は18歳で兵庫県から渡道。自ら斧を片手に山林に入って木を切り出す努力を続け、会社設立後は愛別や比布、新旭川、安足間、上川、足寄、東京目黒などに製材工場を設置。また旭川の近文に広大な敷地を確保し、本社や製材、合板工場を建設するまでに至った。
〝日本の松岡木材〟と称されるまでに名声をあげ、年商34億円にも達していた同社がつまずくきっかけとなったのは、1960(昭和35)年に3億5千万円を投じて建設した最新鋭機導入のハードボード工場。折しも合板の対米輸出が不振を極め、さらにハードボード製品の品質が一定しないなど不評を買い、わずか6年で同工場を閉鎖することになったが、この時の過大な投資負担が後を引いた。
王子製紙や拓銀の力を借り、経営規模を縮小するなど可能な限りの手を打ったが、会社の合理化案に幹部の足並みがそろわなかったこともあり、また政府の金融引き締め政策で資金難に陥り、債務の弁済が不可能になったことから旭川地裁に会社更生法適用を申請、同日、同地裁から財産保全命令が出され倒産した。
この更生法適用申請は管財人のなり手がなく、最終的に商工会議所会頭の盛永要氏も拒否したことから更生法の適用がならず、そのまま破たんの道をたどった。
松岡木材は当時の旭川では最大規模の企業。従業員数も地元資本の中では群を抜いており、近文駅裏手には社員の住宅や社宅、従業員宿舎など約400世帯が立ち並び、独立した感覚のマチを形成していた。結局会社更生はならず、広大な社有地は売り払われ、自動車運転免許センターや道北バス本社などになっている。
専門店会資金を流用 関連企業融手が発覚
 1975年以降、昭和50年代の旭川経済界は様々な形の倒産劇が続出した。最近はほとんど聞かなくなった融手(融通手形)という言葉が横行した時代である。禁断の木の実でもある融手は多くの企業を蝕んだ。そんな融手の存在が如実に表面化したのが、1970(昭和45)年8月2日に倒産(任意整理)した旭川菱雄㈱(旭川市宮下通11丁目、里見和也社長)であった。
1975年以降、昭和50年代の旭川経済界は様々な形の倒産劇が続出した。最近はほとんど聞かなくなった融手(融通手形)という言葉が横行した時代である。禁断の木の実でもある融手は多くの企業を蝕んだ。そんな融手の存在が如実に表面化したのが、1970(昭和45)年8月2日に倒産(任意整理)した旭川菱雄㈱(旭川市宮下通11丁目、里見和也社長)であった。
同社は1949(昭和24)年の設立。特約契約を結んだ国内大手の三菱鉱業と雄別炭鉱の一字を取って菱雄とし、初めは旭川菱雄石炭販売の社名でスタートした。
社長の里見氏は剛腕経営が評判の市内屈指の有力経済人として知られ、旭川の6社のほかに上川町、帯広市にも系列企業を抱え、旭川菱雄だけで年商13億円の売り上げを誇っていた。里見社長自身も高額所得番付の常連だった。
しかし、上川町のガソリンスタンドを約5千万円で買収した時に負債も一緒に引き受けたことが重荷になり、さらに帯広近郊に約3千万円を出資してボウリング場を開設し、2年で閉鎖に至ったことも本体である旭川菱雄の足かせとなった。また、本社隣接地に約5億円で9階建ての大型分譲マンションを建設したが、購入者は戸数の半数に満たず、経営悪化に拍車をかけた。
こうした状況の中で里見社長は、自らが副理事長で金融担当委員長を務めていた旭川専門店会の資金約1億2千万円を自社の運転資金に流用してしまった。専門店会の金庫番でもあり、いずれ人知れず補てんするつもりでいたが、このことが当時の北海タイムスにすっぱ抜かれ、前代未聞の大騒動となった。

この続きは月刊北海道経済2016年10月号でお読みください。