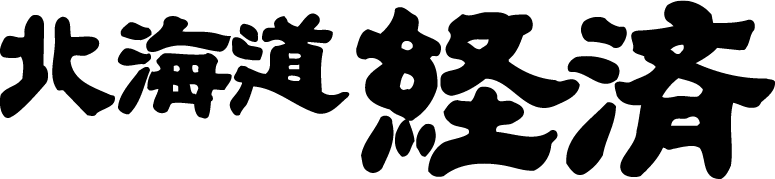ほぼ2人に1人の確率で生涯のうちに患う病気ががん。誰でも家族や友人、同僚、または自分自身ががんと診断されたことがあるはずだ。いま、がんの治療が大きな変革期を迎えようとしている。多くの医師や患者が注目しているキーワードが「パネル検査」(網羅的がん遺伝子検査)だ。患者一人ひとりのがん細胞のなかの遺伝子に注目した新しい手法。まだ課題も多く残っているが、将来的にはがん治療を根本から変えるかもしれないこの新しい技術が、旭川医大にも導入されようとしている。
分子標的薬で進歩
人体は数十兆個の細胞でできている。細胞にも寿命があり、次々と死んでいくが、一方で細胞分裂で新しい細胞が生まれていく。その際、設計図の役割を果たすのが、細胞核の中のDNAに記された遺伝子。細胞分裂では一つの細胞が2つに分かれるが、どちらも設計図通りに、分裂前と同じものが作られる。ところが、このしくみがうまく働かないことがある。遺伝子に何らかの原因で異常が発生し、増殖が止まらなくなるのが「がん」だ。
人間の細胞の一つひとつには、膨大な遺伝子情報が記録されているが、すべての遺伝子の異常ががんの原因になるわけではない。傷ついたときにがんを促進する「がん遺伝子」と、通常はがんを抑制しているが、傷ついた時に抑制が効かなくなる「がん抑制遺伝子」は合計約600あると言われている。
がんの基本的な治療法は、①外科的手術による切除②薬物治療③放射線治療の3つ。ほとんどの患者にはこれらのうち一つを適用するか、複数を組み合わせて治療が行われる。がん治療の現場では、「このような状況の患者に対しては、このような手順で治療を行うべき」という手順(標準治療)が確立されており、どの医師でも採用する治療法は基本的に同じだ。ただ、がんの診断や治療に役立つ新しい技術は次々と開発されており、標準治療も新技術を取り入れるかたちで年々進歩している。
2000年ごろからがんの治療を進歩させたのが「分子標的治療薬」。がんの発生や増殖に関わるたんぱく質を「狙い撃ち」する分子標的治療薬は、それまでの抗がん剤よりも効果が高く、副作用が軽いなどの特徴があり、多くのがんについて分子標的治療薬が開発された。日本で最初に保険承認されたのは乳がん用のトラスツズマブ(2001年)。続いて肺がん治療薬のゲフィチニブが02年に承認された。他にも多くの分子標的治療薬ががん治療に活用されている(がんだけでなく関節リウマチなど他の病気にも分子標的治療薬が用いられている)。
遺伝子が効きを左右
ところが、こうした薬は万能なわけではない。たとえばトラスツズマブが効果を発揮する乳がんは、がん細胞の中で「HER2」と呼ばれるがん遺伝子が異常に増幅しているタイプに限られる。この薬がHER2タンパクと結合してがん細胞の増殖を妨げるためだ。HER2遺伝子の状態は乳がんの治療と予後に大きく影響することから、すべての乳がん患者について検査が行われ、患部から取り出したがん細胞の免疫染色あるいは遺伝子検索からHER2遺伝子の増幅があるかいないか(陽性か陰性)を確かめ、トラスツズマブを使うかどうかが決定される。
体の他の臓器のがんについても、多くの分子標的治療薬が開発されているが、同じ「がん」であってもがん細胞の遺伝子の状態によって「効く、効かない」が左右されるという共通点がある。つまり、がん細胞の遺伝子情報を調べることで、より効果的な治療方法を迅速に選択できる可能性がある。
しかし、これまでのがん治療では、検査の対象となるがん遺伝子はごく一部で、しかも一度に一つの遺伝子しか調べることができなかった。
安く速く遺伝子解析
世界で初めて遺伝子情報を読み取る技術を確立したのはイギリスのフレデリック・サンガー博士(1958年、80年のノーベル化学賞受賞)。その技術はサンガー法と呼ばれるが、大量の遺伝子情報を読み取るには長い時間がかかった。ちなみに人間の遺伝子情報を解読するヒトゲノム計画は1990年に始まり、約3万個(のちに約2万2000個に修正)の遺伝子を読み取るのに13年の歳月と27億ドルの費用を費やした。膨大な時間や費用がかかることから、当時、個々の患者の遺伝子情報を医療に活用するのは現実的ではなかった。
その後、遺伝子情報を読み取る技術は急速に発展した。従来は長い鎖のような染色体を片方の端からもう一方の端に向けて順番に読んでいたが、断片化した上で、同時並行的に読み取ることができるようになった。ベンチャー企業が相次いでこの分野に参入して技術開発競争を繰り広げた結果、いまでは百ドルの資金と1日の時間があればゲノム解析の結果がわかるとさえ言われている。
ここで話をがん治療に戻そう。前述した通り、がんの効果的な治療方法は、がん細胞の中でどのがん遺伝子が「悪さ」をしているかにより変わってくる。そして、一部のがん遺伝子は、複数の臓器でがんを引き起こすことが知られている。例えば乳がんに関わるHER2は、胃がんにも関わっている。EGFR遺伝子は肺がん、前立腺がん、腎がん、大腸がん、乳がんなど多くのがんに関与している。ということは、特定の遺伝子を狙って開発された分子標的治療薬が、複数の臓器のがんで効果を発揮する可能性があるということになる。
この手法は、「個別化医療」とも呼ばれる。がん細胞のなかでどの遺伝子が変異しているかは患者一人ひとり異なり、あらかじめそれを調べた上で、どの薬を使うのか判断するためだ。
大量の遺伝子を一度に
百数十~数百のがん遺伝子とがん抑制遺伝子の状況を一度に調べることで、がんの治療に役立てることを目指すのが、パネル検査(網羅的がん遺伝子検査)だ。国立がん研究センターは、日本人のがん細胞で変異が発生することの多い114の遺伝子を一度に調べることのできる「NCCオンコパネルシステム」を国内企業と協力して開発した。このシステムは昨年末に医療機器の承認を受け、並行して先進医療制度の下で運用が行われてきた。もうひとつ、米国企業が開発した「ファンデーションワン」も承認を受けた。これら2つのシステムを使った検査は、今年の6~7月にかけて保険適応になるとみられ、同時に医療機関でのパネル検査が始まる見通しだ。
北海道では北大病院が全国11ヵ所の「がんゲノム医療中核拠点病院」の一つに指定され、北大病院の連携病院である旭川医科大学病院でも、正式名称は未定だが「がん遺伝子診療外来」が開設され、道北では唯一、パネル検査が6~7月から受けられるようになる予定。
検査のあらましは以下の通り。がん患者から内視鏡などで摘出されたがん細胞は、研究機関に送られて、遺伝子の解析が行われる。その結果をもとに、北大・旭川医大の主治医、病理医、腫瘍内科医、遺伝カウンセリング室医師、臨床検査技師、薬剤師、看護師などが参加するエキスパートチームがテレビ会議で検討を行い、患者の治療方針を決定する。
どんな人でもこの検査が受けられるわけではなく、以下の条件を満たす人だけが保険適応となる。第一に標準治療を受けたが、効果がなかったか、再発した人。または標準治療の確立されていない希少ながんの患者。第二に、全身の状態が「まったく問題なく活動できる」か「肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる」という全身状態のよい患者。このため、がん患者のうち対象となる人の数はかなり限られてくると予想される。ただ、保険適応がなければ自費で検査を受けることも可能だ。自費の場合、検査の費用は数十万円台とみられる。
 しかし、パネル検査に対する過度の期待は禁物だ。検査結果から、患者のがんの主な原因となっているがん遺伝子がわかり、すでに開発されている分子標的治療薬が活用できるのは、検査を受けた人の1~2割にとどまるとみられる。残りの人についてはがんの主要な原因である遺伝子が見つからないか、その遺伝子を狙った薬が現時点では存在しない可能性が大きい。
しかし、パネル検査に対する過度の期待は禁物だ。検査結果から、患者のがんの主な原因となっているがん遺伝子がわかり、すでに開発されている分子標的治療薬が活用できるのは、検査を受けた人の1~2割にとどまるとみられる。残りの人についてはがんの主要な原因である遺伝子が見つからないか、その遺伝子を狙った薬が現時点では存在しない可能性が大きい。
検査の結果、がんの主要な原因であるがん遺伝子が発見され、そのがん遺伝子を狙った分子標的治療薬が存在する場合は、それを使った治療が行われる。ただし、適応外(例えば、乳がん用の薬を他のがんの治療に使う場合)には自費診療となる。
分子標的治療薬が存在しないケースについて有効な治療法を探るのは今後の課題だ。ただ、パネル検査でわかった個々の患者の遺伝子データはがんセンターの「がんゲノム情報管理センター」(C─CAT)に集積され、人工知能技術も活用して有効な薬剤、治療法の開発に役立てられることになっている。
DNAの品質維持
旭川医大病院の腫瘍センター長の鳥本悦宏教授はパネル検査が医療現場に与える影響について、「インパクトは大きい。現在では治療法が見つからない患者に光明が射すかもしれない」と語る。
当面はまず標準治療、効かない患者についてパネル検査という順番だが、鳥本教授は「時間をかけて効果を証明することができれば、標準治療より先にまず遺伝子を調べるようになるのではないか」と予想する。
パネル検査に基づくがんの診断では、病理医が大きな役割を果たす。旭川医大病院病理部の谷野美智枝教授は語る。
「遺伝子解析結果に基づく最善治療につなげるためには、『正確な病理組織診断』、『精度の高い遺伝子採取のための病理検体管理』などが必要になる」
例えば検体を採取する際、がん細胞と正常な細胞が混ざってしまうのは避けられない。このため病理医が、検体のうちがん細胞の占める比率がどれくらいなのかを判定しなくてはならない。また、日本病理学会の調査で、従来は医療機関ごとにDNAの品質にばらつきがあることが明らかになった。このためパネル検査では、学会の定めた規程に厳密に従って病理医らが検体を管理し、DNAの品質を高いレベルで保つことが求められる。
パネル検査で先行するのが米国だ。オバマ政権時代に「プレシジョン・メディシン」(遺伝子レベルの分析を伴う精密医療)が提唱され、研究に大きな進歩があった。日本はある意味「周回遅れ」の状態にあり、ようやく米国を追いかけてスタートすることになる。
がんの治療は進歩を続けている。国立がん研究センターが4月9日に発表した10年生存率はすべての部位の平均で56.3%(2002~05年にがんと診断された人)。この比率は上昇傾向にあるものの、部位別では前立腺が95.7%、乳房が83.9%に達した一方で、肝臓が14.6%、膵臓が5.4%に低迷するなどばらつきが大きいことが鮮明になった。パネル検査の登場で、患者一人ひとりのがん細胞から取り出されたDNAが、比較的難しいがんの治療にヒントを与えてくれるかもしれない。

この記事は月刊北海道経済2019年06月号に掲載されています。