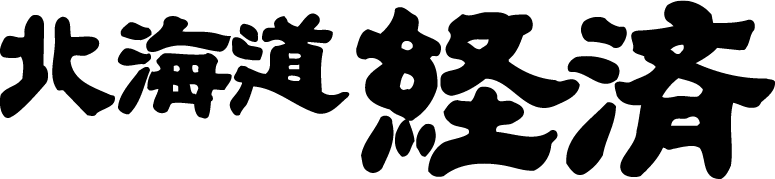つくだ煮や煮豆など、旭川市民にとって馴染みの深い商品を多く手がけてきた旧「㈱藤六食品」(旭川市永山町11丁目)。2009年7月に民事再生法の適用を申請し、当時、生キャラメル人気で勢いづいていた小樽市の「㈱北海道村」(庄子敏昭社長)の工場として再起を目指したが、その北海道村がこの2月25日、事業を停止した。〝名を捨てて実を取る〟選択をしたはずだったが、実も残りそうにない。(記事は3月7日現在)
三重苦に見舞われ
藤六食品は戦後の混乱期、1946年に創業。惣菜づくりから始まり、「北海道自然発」の自社ブランドでつくだ煮や煮豆、海産物をふんだんに使った茶碗蒸しなど、加工食品の製造販売を行ってきた。95年には旭川市永山町に本社と工場を統合した新社屋を建設した。この時点では年間15億円の売上げがあったが、2008年は12億円に減少した。当時、国内外で発生した偽装問題などの影響で食の安全に対する関心が高まり、衛生管理面の強化を図ったことが経営上の重荷になった。
道内スーパー業界の再編などによっても減収・減益を余儀なくされたばかりか、札幌の惣菜事業を拡大するため、関連会社「㈱クラウンデリカ」に多額の出資を行ったことも経営の足を引っ張り、当時社長を務めていた捧範行氏は09年7月に民事再生法適用の申請に踏み切った。
藤六は、俗にいう「食品製造業の三重苦」に直面していた。つまり、設備投資の重圧、原材料の値上がり、そして量販店を中心とする販売先からの値引き要請だ。
しかし、藤六にとって願ってもない救世主として現われたのが北海道村だった。北海道村は07年、倒産した小樽市の池田製菓㈱から「バンビ」の商標権を取得し、キャラメルの製造を開始。生キャラメルブームの追い風にも乗り、事業を急激に拡大させていた。
北海道村は藤六の民事再生申請の3ヵ月前、老舗菓子店の㈱梅屋の全株式を創業家から買い入れ経営権を取得していた。北海道村と梅屋は菓子製造という共通点を持ち相乗効果が期待できたが、藤六との間には商品構成の面で重なるものがあるわけでもなく、相乗効果を見い出しにくかった。それでも庄子氏が藤六支援を決意したのは、捧氏と長い間、家族ぐるみの付き合いをしていたからだった。
北海道村がその後の運営について責任をもつかたちで、民事再生計画は金融機関や取引先の了承を得た。北海道村は、藤六の工場を8000万円で取得し、「北海道村旭川永山工場」に転換。法人としての藤六は解散した。この時点で捧氏らは、藤六の「名」を捨てて、事業の継続という「実」を取ったかにみえた。
自信たっぷりに語る
本誌が当時、インタビューした庄子氏は、生キャラメルブームという追い風が吹いていたためか、鼻息も荒かった。「高級品は特定の消費者だけが参加するクローズドマーケットに販路を広げ、価格競争にさらされている市場に出す商品は、それに適した原材料に置き換えていく」といった経営方針を語るとともに、「十分な注文がないのだから、毎日工場を動かす必要はない。収益を改善するために休みを増やす」などと、独自のプランを自信たっぷりに披露していた。
その後、北海道村は一見したところ好調な経営を続けた。グループ会社の㈱北海道エスケープロダクツとともに本州方面に販売網を構築し、2011年9月期には売上高を前期比15・6%増の25億3800万円まで伸ばした。売上構成はキャラメルが約5億円、プリン・ゼリー・惣菜が合わせて14億円ほどだった。
その一方、借入金も膨れ上がり、元利返済が財務上の重い負担となった。2011年からは中小企業金融円滑化法の下で金融機関に対する返済条件の見直しを図り、同時に人員整理などのリストラも進めた。北海道村が旭川で傘下に収めたもうひとつの企業、梅屋は2012年6月、パチンコ事業を中核とする札幌の三慶グループに売却された。
北海道村旭川永山工場は、「北海道村」ブランドの下で大型カップ入りのメロン・ゼリーやプリンを生産したり、藤六時代からの業務を継続するかたちで全国の百貨店で開かれる物産展に豆の加工食品を出展するなどしていた。従業員はこのころ、「北海道村全体はともかく、旭川工場だけでみれば黒字だ」と周囲に語っていたという。
(この続きは月刊北海道経済2013年4月号でご覧ください)