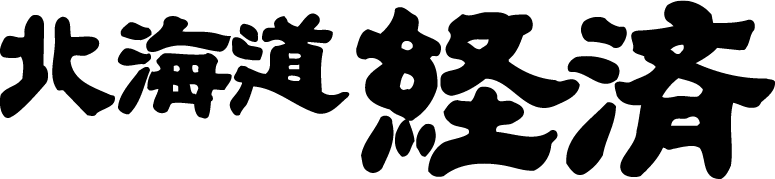旭川の書店業界の雄として長く君臨してきた旭川冨貴堂。「活字離れ」という時代の荒波の中でも南6条、末広、豊岡のロードサイド3店舗を永く維持していたが、2019年の南6条店に続いて、昨年には末広店が、そして今年2月には最後まで残った豊岡店も閉店することになった。昭和期からの本好きにとっては寂しい限りだが、今後も外商部は存続し、学校や官公庁、法人向けとの取引に専念する。

一時は「道内最大」も
2008年ごろ、旭川市内の本好きは選択肢が多すぎて、どこに本を買いに行くべきか迷うことが多かったかもしれない。当時は旭川西武の中に三省堂があった。全国チェーンの宮脇書店も豊岡と緑町に店を構えていた。銀座通り商店街の近くではイトーヨーカドーの地下でくまざわ書店が営業していた。また、市内各地に小規模書店がまだ残っていた。いま、これらの店はいずれも存在しない。旭川西武もイトーヨーカドーも撤退し、内部の書店もなくなった。宮脇は旭川2店を閉じ、道内では札幌に2店を残すのみとなっている。くまざわ書店の店舗は東神楽へ。ここで紹介した以外にも、売り場での販売をやめ、配達に特化している書店が複数存在する。
当時の「最大勢力」はなんといっても冨貴堂だった。この年、3条8丁目にあった本店は閉店したものの、付近のマルカツの中には道内最大規模を誇る書店の冨貴堂MEGAが1996年にオープンしている。前後して1995年には南6条通店、96年には豊岡店、98年には末広店が相次いでオープン、ビデオ・DVD・CDと書籍を組み合わせたロードサイド店の経営にも取り組んでいた。
中でも存在感が大きかったのがMEGA。500坪のうち本の売り場面積が460坪。ブックス平和が抜けた穴を埋めるよう当時のマルカツからの要請を受けて出店した。本州の大型書店の北海道進出を防ぐ狙いもあった。
しかし、書店業界の経営環境は極めて厳しい。MEGAは2011年の1月に閉店。ロードサイド店はTSUTAYAとの提携を通じて音楽・映像ソフトのレンタルや販売を事業を行っていたため30年近く存続していたものの、ネット配信の普及の影響で音楽・映像ソフト関連の事業も下火となり、2019年にまず南6条店が、昨年11月に末広店が閉店した。
他の書店の関係者を驚かせたのは、最後の店となっていた豊岡店が、2月24日をもって閉店することになったとの情報だ。これで全店が営業を終了する。旭川冨貴堂は豊岡店の閉店理由として、ガチャの導入でテコ入れを図ったものの売上減少が続いたこと、25年に店舗土地の賃貸借契約が満期を迎えることを理由に挙げている。今後は学校の教科書、副教材の納品、販売、図書館への納品、官公庁や法人との取引を行う外商部だけが残る。
電子マンガ隆盛
旭川冨貴堂の経営が、「紙の本」離れの影響を受けたことは間違いない。現代の書店にとり大きな収益源となっているマンガ(雑誌+単行本、紙+電子媒体)の2022年の全国売り上げ高は約6770億円。このうち電子コミックが4479億円を占める。
旭川冨貴堂の創業者は京都綾部地方に生まれた志賀金治。同郷で同じプロテスタントという縁を頼り中村家の営む札幌冨貴堂で奉公した。旭川に移り文具と本の店「旭屋」(3の8)を開いたのは1914(大正3)年のこと。旭川の教会の活動を経済的な面から支えるという役割もあったとみられる。30年ごろの一時期、経営が苦しくなり、札幌冨貴堂の旭川店として再出発したのを機に「旭川冨貴堂」に改称した。当初の主力商品は文具で、利益の薄い書籍を補っていた。
長らく、旭川の書店といえば冨貴堂だった。市内の小中学校、高校の教科書の販売で高いシェアを維持しているほか、学校図書館向けの販売も手掛けている。昭和世代の中には、高校の教科書を購入するため、旧本店の狭い店内で並んだのを記憶している人も多いはずだ。
書店業界に吹き荒れる強い向かい風の中、冨貴堂の売り場はよくここまで持ちこたえたとの評価がある。昭和の頃、あちこちにあった小規模な書店はほぼ淘汰された。買物公園で冨貴堂本店としのぎを削っていたブックス平和は、「アラモアナ」として永山で大型店を開いたが、2008年には倒産した。なお、「本家」にあたる札幌の冨貴堂は、札幌パルコ内に入居するかたちとなり、その後パルコの完全子会社化、2003年には早くもこの子会社も書店事業から撤退している。
本の販路は残る
冨貴堂のロードサイド3店も、本だけが上から下まで並ぶ昔ながらの本屋というわけではなかった。音楽ソフトのほか、文具なども豊富に扱っていた。旭川市内でも道内各地でも、現在の主流は複合店。書籍は豊富な商品の一部に過ぎない。
庶民の収入が減り、衣食住への出費を除いた残りのお金はわずか。娯楽が多様化した時代、紙の本の購入に充てられる金額は少ない。ましてや硬派の専門書や文芸書を買うのは少数派。ある大学の教員は「いまの学生は経済的な余裕がないために、数千円の専門書や教科書を読むよう勧めても、購入できる人はまずいない」とこぼす。
とはいえ、旭川から書店がなくなるわけではない。コーチャンフォーや、旭川冨貴堂のかつての関係者が経営するジュンク堂旭川店が存在し、イオン、コープ、ウェスタンなどの商業施設の中にも書店や書籍コーナーがある。市内のあちこちにあるコンビニも有力な本の販売拠点となっている。冨貴堂外商部や配達専門の書店もある。本誌は実体としての本の作り手として、今後その魅力を永く読者に伝えていきたい。