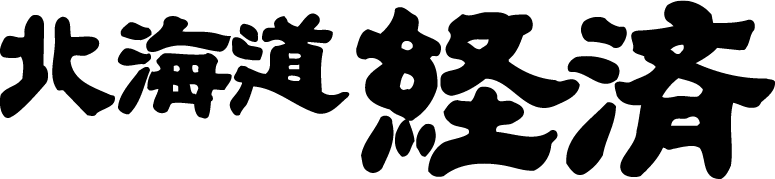1950年(昭和25年)に制定された建築基準法は、時代の変化とともに改正を重ねて来た法律だ。建物の構造・仕様などの基準が一部変更され、4月1日に施行された。原則全ての新築住宅に省エネ基準への適合義務化などが盛り込まれ、住宅新築や増築・改築の際に必要な建築確認申請の手続きに大きな変化が出てくる。建築市場は地域の経済動向を図る上で重要な産業といえる。実際に施行されなければ見えないことも多いだろうが、申請に深く係る行政や民間の企業、一般ユーザーの対応などから今後の見通しなどを探ってみる。

CO2削減目指し
建築基準法の目的・第一条には「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の命、健康及び財産の保全を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とある。最低限の基準を示したものなので完全な安全を保証するものではなく、実際に利用者が建物を建設し使用する場合は、同法のほかに消防法、都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水道法、下水道法、浄化槽法、バリアフリー新法、品確法、耐震改修促進法、建築士法、建設業法など多くの関連法規の規制を受けている。
一般ユーザーにとって住宅建築はごく身近な話題になるが、多くの法規制を受けていることを意識している人は少ない。ましてや今回の建築基準法改正からの影響を実感している人はいまのところ少ないのではないか。
今回の改正は2022年6月に公布された「脱酸素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」というなんとも長い表記による改正だ。これは、国が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、同年の「建築物省エネ法改正」に沿って公布された。住宅における省エネルギー基準の厳格化で全住宅が一定のエネルギー効率を満たすことで、国内エネルギー消費量の約30パーセントを占めるといわれる建築分野での省エネ対策を推進するものだ。改正で原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務化し、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性検査が必須になった。
改正のポイントは①新築住宅や商業建築の省エネ基準適合の義務化②断熱等級4を最低基準とした省エネ基準の厳格化③4号(一般的な木造2階建ての一戸建て住宅)特例の縮小で建築確認の省略が、平屋かつ延べ床面積200平方メートル以下の住宅のみになる④300平方メートル超の建築物の許容応力度計算の義務化で持続可能な社会の実現・エネルギー効率や安全性の向上・住宅分野全体の省エネ性向上・耐震性や構造強度の向上・地震や台風といった外力に強い住宅をつくる─が主なもの。つまり、省エネを国全体で進めるための方法として、新築はエネルギー性能の高い物だけを認めることが原則となった。
ポイントや目的が明確に示され、持続可能な社会の実現とともにエネルギー効率や安全性を高めて維持費の軽減を実現する。個別の工務店やハウスメーカーの設計で自由度が高まり顧客(ユーザー)に魅力ある提案が可能になる。改正後の基準に適合したリフォームで資産価値が高まるとともに省エネ性、耐震性が向上し長く快適な住環境を実現できる─などのメリットが強調されている。が、反面、改正に伴う問題点もある。
住宅建築の第一歩となる建築確認申請の提出が大きく変わることだ。①、②では従来に比べて事務量が1・5倍程度に増えたり、費用もかさむ。更に③によって新築、増改築の申請件数が増えて申請側、受理側双方に体制、人員的に影響が出る。
申請に必要なチェック項目の増加は、図面枚数の増加と整合性確認などに時間を要するようになる。従来、省略が認められていた部分の改正で許可までの日数7日が35日に延びる。その影響で工期の延長、建築費の上昇が避けられない状況が生まれる。また、省エネ設計や構造設計の厳格化で着工後の仕様変更があると申請再提出のケースが出ることも考えられる。例えば、これまでは「軽微な変更」でできた冷暖房設備の機種変更や窓のサイズ変更などが申請対象になる可能性がある。その場合は、更に工期が延びる事態も出てくる。
審査9割担当の民間業者が廃業
そもそも、受理側には慢性的な人手不足の現状がある。建築確認申請の審査には建築基準適合判定資格者(1級、2級)という国家資格が必要。これは例年の合格率が30パーセント前後の難易度の高い資格だ。受験資格が1級建築士所持者で実務経験も求められることから取得希望者が少ないというのが実情だという。資格者不足に何とか対処しようと申請の受付窓口となる自治体は「民間活用」を積極的に取り入れてきた。旭川市では、2008年に㈱建築確認検査機構あさひかわ(以下、あさけん)が、北海道知事の指定検査認定機関の指定を受けたのを契機に4号全件数の9割前後の審査を担当してきた。しかし、同社が今年3月末に廃業し新規案件の受付けを終了した影響で、受付側の体制の先行きが不安視されている。旭川市は、札幌の指定検査認定機関へのオンライン申請を呼び掛けるのと並行して、市窓口の増員を考えているようだが、即戦力の人員確保は見えていない。
今年4月の改正法施行が決まった22年から3年間の準備期間があった。実際にふたを開けてみないことには対応できないこともあったとは思うが、混乱回避に万全の備えは簡単ではなかったようだ。あさけんが廃業に至った主な要因は、後継技術者の不足と資格保有者の高齢化だという。受験資格が厳しく難易度の高さが壁になっていると同時に職種としての魅力の乏しさも取得者の増加に結びつかないのだという。
行政、民間の企業(設計、施工部門)、ユーザー(施主)などがそれぞれの立場で改正法に対処していくことが重要になるが、それぞれの捉え方には温度差がある。行政は、昨年までに改正法の周知のための説明会を開き、疑問点などの解消に当たる一方、市外(札幌)の指定検査認定機関へのオンライン申請を勧めるなどの道を探ってきた。しかし、前述したように申請数の変化を正確に予想するのは困難で、しばらくは手探り状態が続く。
申請側の企業で設計部門を担当する企業や団体からは、改正法が施行されても「技術的な課題は少ない」との楽観的な声も多く聴かれる。従来から北海道の住宅は、「高断熱・高気密」に優れ、「北方型住宅」としてクオリティの高い成果品を提供している。その技術力から省エネ設計に対しての不安の声は大きくない。申請内容の厳格化に対応することと許可までの時間(日数)を考慮した余裕ある作業工程を心掛けて対応すれば十分との見方もある。ただ、構造設計の厳格化に関しては状況に合わせた新たな取り組みが必要になる可能性もありそうだ。
施工部門の工務店やハウスメーカーの企業、団体の反応は様々だ。昨年来、研修の場などで頻繁に対応策の話題が出ていた団体などもあったようだ。企業規模が大きなところは申請のオンライン化や省エネ設計、構造設計などにも対応できるが、いわゆる「一人親方」の業者は対応が難しく、高齢化と相まって「廃業か」といった深刻な言葉も出ているという。
かけこみ申請なく
旭川市の建築確認申請の大部分を受け付けていたあさけんでは、改正法の適用が4月1日以降の着工が対象になることから「3月中に着工できるように駆け込み申請があるのではないか」と予想し準備していたが、同社への1月から3月までの申請件数は例年通りで目立った変化は見られなかったという。しかし、市がまとめた2月の4号申請数が前年と比べて34件増の81件となり、市外の指定検査認定機関経由の申請があり、市や設計・施工者がオンライン申請を勧めた効果が出ているようだ。いずれにしても4月に入ってからの申請では雪解け直後の着工が出来ないのは間違いない。設計・施工者とも切れ目ない仕事確保のための準備が重要になるだろう。
ユーザー(施主)は、建築確認申請そのものを直接、提出するケースが稀なこともあり改正の認知度は低い。着工までに時間が掛かったり申請費用が増えたりして初めて知ることになるのではないか。そういった小さな問題の積み重ねで新築・増築・リフォームの意欲が削がれては、地域経済全体の熱量が萎んでしまう。
旭川市の年度別建築確認申請件数の4号分(計画通知含む)は、2020年度1227件、21年度1236件、22年度1027件、23年度876件、24年度(2月末まで)811件と推移。23年度に1000件を切り、減少傾向が続いている。資材・機材の不足や価格高騰、人手不足による人件費の高騰などから建築費が膨れ上がり、建て替え、新築からリフォームに変更したり、新築自体を断念するといったケースも増えたという。住宅建築は関連の業種が多く、広範囲に渡るので地域の経済に直接、大きな影響が出ている。
国の「2050年カーボンニュートラル」による省エネ政策は将来を見据えて重要な施策だろう。しかし、今回の基準法改正の内、耐震性能向上の構造設計厳格化はともかく、省エネ対策面の「4号特例の縮小」は、北海道で必要だったのだろうか。道内でこれまでに積み上げてきた高断熱・高気密住宅の実績は、改めて厳格化する必要がないほどの精度がある。「積雪寒冷地以外の冬の住宅室内は寒い」と聴くことがある。これは、断熱性の低さが原因だと推察でき、断熱性が低いことが夏の暑さにも対応できないと考えるのは間違いだろうか。積雪寒冷地以外で「省エネ基準適合義務化」が徹底されれば、目的は達成できるのではないか。法律が絶対であるのは言うまでもないが、地域の特徴や特性に適応した、きめ細やかな運用が出来たほうが、課題解決に役立つ可能性もある。