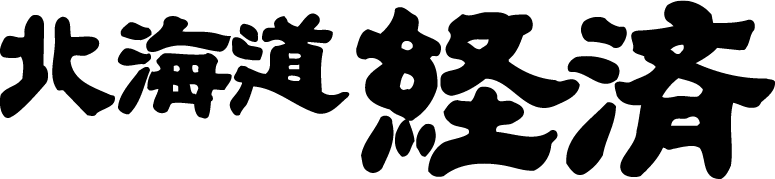候補者個人よりも、与党か野党かで投票先を決める政党選挙の色合いが強かった今回の衆院選道6区では、自民党公認の東国幹氏が圧勝した。この自民党の大勝利は、昭和の自民3派の時代から懸案とされてきた、旭川における「保守一本化」の課題に取り組む作業の総仕上げとも映るものだった。元来、保守勢力が根を張ってきた旭川だが、その根からようやく1本の太い〝幹〟が顔をのぞかせてきた。自民党の東氏が立憲民主党の西川将人氏を予想以上の大差で振り切った「東西決戦」を振り返ってみる。
自民勝利の結果は士別・旭川から伝染
10月31日夜、投票箱のふたが閉まる午後8時を待っていたかのように全国の大手報道機関は、競って東の「当確」を打ち出した。もちろんまだ開票作業は何一つ進んでいない。それでも〝結果〟を予想できるのは緻密な取材・調査活動の賜物と敬意を表すところだが、陣営の動きを見て情勢をつかむことぐらいしかできない弱小の地元雑誌の見立てでも、この6区の新人対決の情勢を判断し優劣をつけることは難しいことではなかった。まずは得票結果から。
東 国幹(53) 128,670
西川 将人(52) 93,403
斉藤 忠行(30) 9,776
自民公認の東は、立憲民主公認の西川に3万5000票以上の差をつけ振り切った。選挙区内有権者の約7割が集中する旭川だけで見ても、その差は約2万6000票で、得票数はほぼ6対4の割合だった。
ひと月ほど前に行われた自民・今津寛介、立憲・笠木薫による旭川市長選でも、自民の今津は立憲の笠木に2万8000票以上の差をつけて勝利しており、この時も6対4の割合だった。また、旭川市長選より2週間早かった士別市長選でも自民の渡辺英次が立憲の松ヶ平哲幸を破り、得票の割合は渡辺5・5、松ヶ平4・5だった。
 この時期、伝染という言葉は不適切かもしれないが、今年9月に上川管内で行われた二つの市長選の結果がそのまま衆院6区の選挙戦に伝染したかのようにも感じられる。そしてその伝染はかなり高い確率で予知できた。それは、過去の選挙データによって示される歴史の波というか、人心のバイオリズムである。
この時期、伝染という言葉は不適切かもしれないが、今年9月に上川管内で行われた二つの市長選の結果がそのまま衆院6区の選挙戦に伝染したかのようにも感じられる。そしてその伝染はかなり高い確率で予知できた。それは、過去の選挙データによって示される歴史の波というか、人心のバイオリズムである。
士別も旭川も6区も新人同士の戦いで、有権者が投票先を決める判断材料は少ない。いったいどの波に乗ればよいのか、それを判断する基準は自民か立憲かの二者択一しかなく、今回は自民が勝つ順番だった。それは地方選挙でよく見られる〝流れ〟のようなものである。
「いじめ問題」軽くみていた?
政策を戦わすことが基本であるはずの選挙戦に、政策とは違った〝道具〟が使われていた。一番目立ったのは旭川市におけるいじめ問題を取り上げた西川候補への追及。この問題1点に絞って立候補したNHK党の斉藤忠行が街頭演説やSNSで前旭川市長の辞職を〝投げ出し〟と批判するのはわかるが、東陣営でも政策を訴えるのと同じくらいの時間を使い「いじめ問題の早期真相解明を」と今津寛介新旭川市長とともに訴え続けたのは紛れもなく西川批判ととれるものだった。
確かに西川前市長には、追及される要素はある。しかし西川がこの問題に対して無策だったわけでもなく、市長として当たり前のことはやっていた。ただ、第三者委員会の調査の結論が出る前に市政を離れることになったのは、時機としてまずかった。旭川大学公立化、優佳良織工芸館に目が向きすぎたこともあって、社会問題になっていた女子中学生のいじめ問題を軽くみていたのかもしれない。
他候補からの投げ出し批判が選挙結果にどう影響を与えたのか何とも言えないが、先の旭川市長選でNHKが行った出口調査では「いじめ問題も投票に考慮したか」を尋ねたところ、「大いに考慮した」が37%、「ある程度考慮した」が39%あったといい、実に7割を超える有権者が投票する際の判断材料の一つとしていたようだ。
5週間前の市長選では西川の後継者となった笠木が、西川の残していったいじめ問題未解決という逆風にさらされていたことは明らかだが、衆院選でもその流れがより勢いを増して続いていたと言えるのではないか。選挙中の西川は「国において教育界のあり方、学校現場のあり方、教員の採用の問題など様々な面で検証し、改善していく」と抵抗するだけで精一杯の様子だった。
敗北が決まった夜、西川選対本部長の佐々木隆博は「政策以外の選挙戦になったことが残念だった」と悔しさをにじませていた。
選挙巧者の東 農協対策が奏功
東の大勝利にはいくつかの要因が考えられるが、冒頭にも書いた候補自身の要素もさることながら、政党を選ぶ「政党選挙」であったことの効果が大きかった。また、大票田旭川における保守一本化の実現、さらに今津時代にはあまり頼りがいのなかった選挙区管内23市町村の農協を完全に押えたことも計り知れない実利となった。
上川管内の主要産業である農業。その農家関係者を束ねる農協は、革新系の農家組織とは異なる関係にあるものの、選挙戦では絶大な力を持つ存在となる。昨年8月から6区の自民党候補者となった東が最も力を入れて手掛けたのが農協の取り込み。ふらの農協組合長で上川地区13農協の束ね役でもある植﨑博行を連合後援会長に担ぎ上げた効果は結果を見れば明らかである。
東のターゲットは初め、現職の衆議で周囲に「次もやる」と漏らしていた佐々木隆博だった。道議から国政転出をねらう東にとっては、長年にわたり農家との信頼関係を築いていた佐々木の牙城を切り崩すことが勝利を得るための必要条件でもあった。
「佐々木さんはいい人だけど、野党だからね」という農民感情に、東は巧みに食い込んだ。途中で相手候補は都会派の西川に代わったが、西川が農協に入り込む余地はすでに残ってなかった。立憲民主が党農労の3軸の一つとして挙げる〝農〟の組織力も管内に張り巡らされた農協組織には及ばなかった。植﨑連合後援会長が唱える「上川管内から与党の代議士を」の声は農家はもちろん経済界からの共感も呼んだ。
選挙中には「日が昇る東と日が沈む西、あなたはどちらを選びますか」といった東西決戦を茶化したようなフレーズも見かけたが、結局のところ、道議選3連続トップ当選の選挙巧者の東と、旭川経済界の保守一丸体制を実現させた陣営がつかみ取った大勝利だったといえるのではないか。
「解散のある衆議院はいつ選挙があるかわからない。常在戦場のつもりで活動していく」─東の選挙戦は果てしなく続いていきそうだ。

この記事は月刊北海道経済2021年12月号に掲載されています。