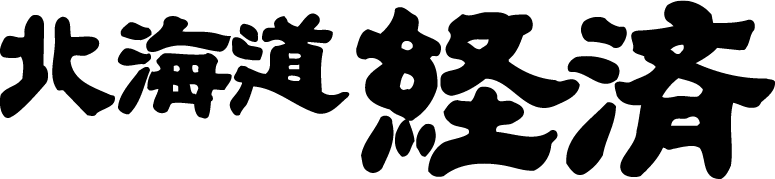本誌が吉田晃敏・旭川医科大学前学長にまつわる記事を何度か掲載したのはいまから3年あまり前のこと。旭川医大を卒業したベテラン医師たちの間で「吉田氏が再就職したらしい」との情報が広がった。本誌が電話取材すると、吉田氏は原点に戻った最近の状況について慎重に言葉を選びながら明かした。

「心配しなくていい」
今年夏のある週末、記者は北彩都地区の大池を見下ろすカフェを訪れた。本から視線を前方に移すと、すぐそこに見覚えのある顔があった。吉田晃敏・旭川医大前学長だ。その傍らには、すでに第一線から退いた元議員がいた。記者は歩み寄って吉田氏にあいさつした。「おお、久しぶり」。血色が良く、声も力強い。
「いま何やっているんですか」との問いに、「時期が来たら言うよ。元気でやっているよ」とだけ答えた。そのあとは元議員を交えて、米国留学時代などの昔話が続いた。
吉田氏は長年連れ添った夫人と離婚、その後、別の女性と結婚したものの、離婚したとの情報も伝わってきていた。吉田氏はこうした情報を率直に認め、「自由に戻った」と笑った。記者は単刀直入に飲酒問題についても尋ねた。「学長時代に飲んでいたのはやけ酒。もう2年間、酒は飲んでいないよ。肝機能の検査も結果は『OK』だった。心配しなくてもいい」。最近の暮らしぶりや活動内容については結局聞けずじまいだった。
学長就任前にも、学長としての最終盤にも、記者は吉田氏から直接話を聞いているが、当時印象に残ったのは発話が明らかに遅くなっていることだった。口の動きが脳の動きに追いついていない印象を受けたが、今年夏の再会では以前の受け答えの様子にかなり近づいているように感じた。
医大の後輩が協力
その後、複数の医療関係者から、吉田氏が医療現場への復帰を目指しており、医師仲間やかつての教え子にも協力を要請したとの情報を得た。しかし、医大OBの大半は協力を拒否、または協力したくても困難な状況だった。旭川医大の現執行部はいまも「反吉田色」が濃厚で、吉田氏を下手に助けて執行部に目を付けられれば、今後の医療や研究の仕事に差し支えるかもしれないと、尻ごみしたのだろう。
唯一、手を差し伸べたのが医師の的場光昭氏だった。本誌を含め、ほとんどのマスコミが吉田批判に染まる中でも、旭川医大における数期後輩である的場氏は吉田氏を擁護し続けた。自身も自治体が設立した診療所での医療の経験が豊富な的場氏が奔走した結果、吉田氏は今年4月から中川町立診療所に医師として勤務している。つまり、記者が再会した時点で、吉田氏は再就職していたことになる。
最近、記者は吉田氏に電話取材をした。「中川町で医師として働いていると聞いたが…」。吉田氏は、旭川市と中川町の間を往復し、日中・夜間の当直を含めて月に約10日間勤務していること、専門の眼科だけでなくすべての領域を担当していることは認めたが、それ以外はあまり語りたくない様子。それでも二つだけ、付け加えたことがある。「旭川医大はもともと、医療の地域格差を解消することを目的に設立された医科大学。その目的のために現場に戻り、初心に戻って勉強しながら、患者さんと接している。また、私が医者として経験したことを多くの人と分かち合いたいという思いがある。今年の8月には中国に招かれて講演してきた」。
学長経験者の処遇としては異例だが、旭川医大は吉田氏に「旭川医科大学名誉教授」の肩書を与えていない。名誉教授なら再就職も容易だったのではないかと尋ねたが、「いまの旭川医大については何も言いたくない。アングリー(怒っている)吉田はもういない」とだけ言った。
ライフワークに戻る
中川町役場によれば、中川町立診療所は町によって設立され、現在、医療法人櫟(いちい)会によって運営されている。院長の赤間保之氏の下で数人の旭川医大出身の医師が診療を行っている。元々は10床の入院病床があったのだが、看護師が確保できないため、現在病床は休止中だ。
中川町の人口は1957年に記録した7337人をピークに減り続け、今年8月時点では1286人。若年女性の人口は2020年の88人から2045年には46人まで減少すると見られている。こうした状況の中、多くの住民は町内で受けられる医療に不安を感じ、都市部に流出していく。吉田氏が乗り込んだのは、こうした僻地の医療の厳しい現実に直面する地域だった。
吉田氏が旭川医大時代にライフワークとして取り組んだのが、眼科領域での遠隔医療だ。その目的は、大都市圏でも僻地でも同じ水準の医療を提供することにあった。そしていま、吉田氏は高速インターネット回線や高精細カメラに頼らず、自ら中川町に乗り込んで医療の地域格差解消を目指しているというわけだ。
旭川医大を舞台にした全国区の騒動から3年余り。その最中もその後も、吉田氏の歩む道は平坦なものではなかったが、いまは一人の医師として、原点に帰って患者と向き合っているようだ。